2018年09月06日
結城と福井を繋ぐ伝説と信仰―猫塚伝説と袋羽神―
結城と福井を繋ぐ伝説と信仰―猫塚伝説と袋羽神―
*********
今年の夏は全国的に自然災害が多いですが、今週に入ってからは、台風21号による関西方面の被害に加え、北海道の大地震まで起きてしまいました。
被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一刻も早い復旧を切に願います。
*********
さて、だいぶ以前になりますが、文献1を読んでいる時に、下記のような話を見つけました。
猫塚伝説
―あらすじ―
江戸時代の初めごろ、越前国(今の福井県福井市)に、川澄角平という片目の武士がいた。
ある時、江戸勤めになり、妻子が留守を守っていたある日、ひょっこり角平が帰ってきた。
しかし、『内密に帰ってきたので、親類や近所に知らせてはいけない』という。
ちょうど、料理しようとしていた鯉があったので、その鯉料理を出す時に、妻は角平がおかしいのに気づいた。
角平はもともと右目がつぶれていたが、「江戸から帰ってきた」という角平は左目がつぶれている。
角平の妻が人をやって弟に連絡をし、戻ってくると、男は逃げた後だった。
鯉を食べるためにタヌキが化けていた。
さて、角平が本当に江戸から帰ってきて何年か経ったある日のこと。今度は瓜二つの女房が二人いるという事件が起きた。二人とも声も所作も全く同じで、見分けがつかない。
そこで角平は自分の故郷 結城の産土神の袋羽神を勧請し、祈った。
ある夜、酒を飲みながら二人の女房を見ていると、ハエが飛んできて、一人の方の耳に止まった。するとその耳がピクピクと動いたので、化けものだと分かり、角平が切りつけると、それは年を経た大きな猫だった。
角平は化け猫を葬って、その上に衣羽(袋羽)大権現を祀った。
話の前半と後半は違うエピソードです。
で、私が注目したいのは、後半のエピソードに出てくる
『故郷 結城 の産土神』の
『衣羽(袋羽)神』です。
衣羽(衣羽)は、『ほろわ』と読むそうです。
【歴史~結城と福井の繋がり】
ここでまず、川澄角平さんの故郷が、(現在の茨城県の)結城であるということについて、考えてみます。
物語の時代 『江戸時代初めごろ』 に注目。
下総国結城(現在の茨城県結城市)の大名だった結城秀康は、江戸時代初め、越前国北庄(現在の福井県福井市)に移り住みます。 そして、越前北ノ庄藩初代藩主、越前松平家宗家初代となります(Wikipediaより)。
たぶん、川澄角平という人は結城家の家臣で、共に越前国に移ったのでしょう。
だから、家で起きた怪奇現象の時に、自分の故郷の神様だった『袋羽神』に祈ったのですね !
!
福井県に伝わる伝説ですが、その中にある『故郷の結城の産土神に祈った』という一文に、戦国時代終りから江戸時代初期の頃の地方史と当時の信仰が見えて、とても面白いです。
【袋羽神とは】
『ほろわ』の字は、『袋羽』と書いたり『衣羽』と書いたりするようです。
伝説では『袋羽』で、現在ある神社の額は『衣羽』になっています。
結城地方に同様の伝説がないか、また、ほろわ/袋羽神についての信仰・風習があるかについて、地図や文献でも調べているうちに、『ほろわ(ほろは)』について詳しく調査された方の論文(文献2、3)を見つけました。
それによると、『ほろわ(ほろは)神』は、東日本、特に東北から茨城にかけてかつて信仰されていた神様だったようです。
また茨城県内の『ほろわ(ほろは)』にまつわる神社等を詳細に調べられていて、結城市付近にはないようですが、筑波山の近く、つくば市北条にある八坂神社の境内社に、保呂羽(ほろは)神社があるとのこと。
川澄角平さんが結城に住んでいた時代(戦国時代終り~江戸時代初期)には、まだ『ほろわ神』信仰が続いていたのでしょう。
東日本の失われた民間信仰の痕跡が、遠く北陸の福井県の昔話に伝わっているのも面白いです!o(^o^)oワクワク。
【猫塚と袋羽/衣羽(ほろわ)神社】

さて、猫塚伝説の伝わる袋羽/衣羽(ほろわ)神社は、現在、福井市内にある神明神社という神社さんの境内に、合祀される形であります。
先月7月に、福井県福井市の方に行く機会がありました ので、猫塚伝説が伝わる袋羽(衣羽)神社がある、神明神社を訪れました(^^)v。
ので、猫塚伝説が伝わる袋羽(衣羽)神社がある、神明神社を訪れました(^^)v。

神明神社 拝殿
大きな神社さんです。

神社の境内に、3つの摂社を合祀したお社(合祭殿)があり、その中に袋羽神社もありました。
こちらの神明神社さんのHP(http://www.shinmei-jinja.jp/yurai/ )によると、ご祭神は『袋羽大神』とのこと。

合祀されたお社の額。
向かって一番左に『衣羽神社』の文字が。

中に入ると説明版がありました。
『袋羽神社(猫塚さん)
古くは「正保二年(一六四五年)三月吉祥日施主川澄角平興勝」の銘あり。天保・弘化の頃より庶民の信仰得て諸願成就の奇瑞あり。
「袋羽大神」は妻に化けた猫を退治した川澄角平が願を懸けた郷里・結城の産土、袋羽神を称えて建立したものと伝えられている。
現在も「猫塚さん」の名で親しまれ。子供の夜泣平癒に霊験があり、鰊(にしん)をそなえ、絵馬を掲げて子供の無事成長を祈願する人の参拝が絶えない。』
とのこと。
説明板の隣には、サンマを奉納するための立派な木製の箱もありました。
傍には同じく木製の板に書かれた
『お子様の夜泣き平癒お詣りの方は この中に「にしん」をお供えください。絵馬は社務所でお受けください』
の添え書きも。
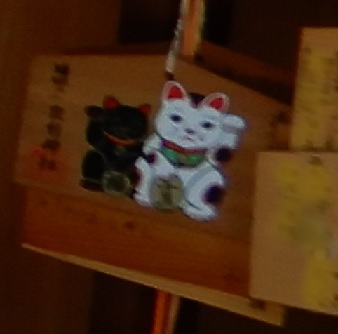
『招き猫』が描かれた絵馬もたくさん奉納されていました。
赤ちゃんの夜泣きなどに霊験あらたかとのことで、お参りしました(^^)
それにしても、
・退治された化け猫
・退治した(であろう)袋羽神
が習合して、
・『子供の夜泣きに効く』
という信仰に繋がった
その経緯にも、興味がわきます♪
そして現代では、化け猫ちゃんは、『招き猫』の絵柄になって絵馬に描かれている・・・というのも、日本の信仰っぽくて興味深いです 。
。
せっかく来ることが出来たので、お守り購入とご朱印も頂きたかったのですが、社務所に行って呼び鈴を鳴らしてもどなたも来られず 、電車の時間も迫っていたので、そちらは泣く泣くあきらめました
、電車の時間も迫っていたので、そちらは泣く泣くあきらめました ・・・(拝殿でお祓いをされていたようなので、そちらでお忙しかったのかもしれません)。
・・・(拝殿でお祓いをされていたようなので、そちらでお忙しかったのかもしれません)。
【養蚕と猫と信仰】
文献2,3 によると、『ほろわ』の語源はいろいろ考えられるようで、どういった神様だったかも不明のようですが、『ほろわ』に当てられた『袋羽』や『衣羽』という字に、繭を作り絹を生む『蚕』を連想しませんか?
私の勝手な想像ですが、養蚕業や織物が盛んな土地に伝わった『ほろわ神』は、養蚕の神様にもなって、『袋羽』や『衣羽』という字が当てられた・・・という可能性はありませんかねぇ(^^)。
(文献1でも触れられていますが、絹織物『羽二重』で有名な福井も、昔から絹織物で有名な地域です。)
そして茨城県結城市は、いわずと知れた絹織物の結城紬で有名。
一帯は養蚕業が古くから盛んでした。
養蚕業が盛んだった土地では、蚕の天敵の鼠を食べる猫が大事にされていたと聞きます。
なので、猫を祀るところもあるそうです。
なので、結城付近にも、蚕を(鼠から守る)猫を祀る祠やお社があってもよさそうなのですが、どうもない(今はない?)ようです。
結城地方に伝わる昔話に、猫の伝説はないかな?と、探していたら偶然にも結城に伝わる『ねこづか』伝説がありました!(文献4)
しかも、こちらも化け猫!
結城の『猫塚』伝説は、
お寺のお葬式で、遺体をくわえて逃げようとした黒猫の化け物を、和尚さんが斬りつける話。
逃げた化け猫が残した爪を集めて埋めた『ねこづか』が昔あったとのこと。
・・・残念ながら、福井の猫塚伝説とは直接関係はなさそうです・・・。
それにしても、羽二重の里の福井でも、結城紬の里の結城でも、お蚕さんを守るニャンコではなく、化け猫伝説なんですねぇ(^m^)。
・・・話が脱線しました(^^;)
養蚕に関する信仰に話を戻します。
結城からもよく見える筑波山の山麓には、絹織物の神様を祀る 蚕影山神社があります。
絹織物が一大産業だった明治時代から昭和の中ごろまでは、蚕影山神社には多くの参拝者が訪れて大変賑わったと聞きます。
そして、全国(特に関東甲信地区)には、この蚕影山神社を分祀した『蚕影神社』が建てられたそうです。
ちなみに以前書いた記事:
 → 東京・立川の『猫返し神社』と筑波山麓の関係!
→ 東京・立川の『猫返し神社』と筑波山麓の関係!
にある、東京の立川市の蚕影神社は、阿豆佐味天(あずさみてん)神社、通称:立川水天宮の敷地の中にある境内社です。
もともとは直接『蚕―鼠―猫』繋がりはなく、現代になり偶然のきっかけで『猫の神様』的神社になっていますが、本来は蚕の神様を祀る蚕影神社です。
残念ながら・・・といいますか、総本社の蚕影山神社には、猫にまつわる伝説も信仰も伝わっていないのですが、こう見ていくと、日本の信仰って、とても面白いですね(^^)
【おまけ】
あと、もうひとつ、結城―福井の歴史的繋がりには、つくばも関わりがあります 。
。
先日のNHKの番組『歴史ヒストリア』でも、『戦国最弱(?)の大名にして『戦国の不死鳥』の異名を持つ』と紹介された、最近人気上昇中?!の小田氏治も、結城秀康とともに越前国に移り住み、そこで亡くなっています。
小田氏の居城だった小田城址歴史ひろばについても、以前書いた記事
 → 小田城跡歴史ひろば” の歩き方(入門編)
→ 小田城跡歴史ひろば” の歩き方(入門編)
そして、福井の郷土料理と結城の郷土料理を融合させたみた 創作料理
 → 【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば(87)】 結城&福井の郷土食コラボ♪ すだれ麩ときゅうりの胡麻からし酢味噌和え
→ 【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば(87)】 結城&福井の郷土食コラボ♪ すだれ麩ときゅうりの胡麻からし酢味噌和え
も良かったらお読み頂き、旅とグルメのご参考に(^^)v
***********************************************************************
【参考文献】
1.「妖怪ウォーカー」 村上健司 著 角川書店
2.「袋羽明神とホロハ塚」 徳原聡行 著 (茨城民俗学会誌 第26号 p.46-p.48)
3.「『ほろわ』考」 徳原聡行 著 (常総の歴史 第2号 p.82-p.90)
4.民話「ゆうき」 結城市教育委員会
*********
今年の夏は全国的に自然災害が多いですが、今週に入ってからは、台風21号による関西方面の被害に加え、北海道の大地震まで起きてしまいました。
被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げるとともに、一刻も早い復旧を切に願います。
*********
さて、だいぶ以前になりますが、文献1を読んでいる時に、下記のような話を見つけました。
猫塚伝説
―あらすじ―
江戸時代の初めごろ、越前国(今の福井県福井市)に、川澄角平という片目の武士がいた。
ある時、江戸勤めになり、妻子が留守を守っていたある日、ひょっこり角平が帰ってきた。
しかし、『内密に帰ってきたので、親類や近所に知らせてはいけない』という。
ちょうど、料理しようとしていた鯉があったので、その鯉料理を出す時に、妻は角平がおかしいのに気づいた。
角平はもともと右目がつぶれていたが、「江戸から帰ってきた」という角平は左目がつぶれている。
角平の妻が人をやって弟に連絡をし、戻ってくると、男は逃げた後だった。
鯉を食べるためにタヌキが化けていた。
さて、角平が本当に江戸から帰ってきて何年か経ったある日のこと。今度は瓜二つの女房が二人いるという事件が起きた。二人とも声も所作も全く同じで、見分けがつかない。
そこで角平は自分の故郷 結城の産土神の袋羽神を勧請し、祈った。
ある夜、酒を飲みながら二人の女房を見ていると、ハエが飛んできて、一人の方の耳に止まった。するとその耳がピクピクと動いたので、化けものだと分かり、角平が切りつけると、それは年を経た大きな猫だった。
角平は化け猫を葬って、その上に衣羽(袋羽)大権現を祀った。
話の前半と後半は違うエピソードです。
で、私が注目したいのは、後半のエピソードに出てくる
『故郷 結城 の産土神』の
『衣羽(袋羽)神』です。
衣羽(衣羽)は、『ほろわ』と読むそうです。
【歴史~結城と福井の繋がり】
ここでまず、川澄角平さんの故郷が、(現在の茨城県の)結城であるということについて、考えてみます。
物語の時代 『江戸時代初めごろ』 に注目。
下総国結城(現在の茨城県結城市)の大名だった結城秀康は、江戸時代初め、越前国北庄(現在の福井県福井市)に移り住みます。 そして、越前北ノ庄藩初代藩主、越前松平家宗家初代となります(Wikipediaより)。
たぶん、川澄角平という人は結城家の家臣で、共に越前国に移ったのでしょう。
だから、家で起きた怪奇現象の時に、自分の故郷の神様だった『袋羽神』に祈ったのですね
 !
!福井県に伝わる伝説ですが、その中にある『故郷の結城の産土神に祈った』という一文に、戦国時代終りから江戸時代初期の頃の地方史と当時の信仰が見えて、とても面白いです。
【袋羽神とは】
『ほろわ』の字は、『袋羽』と書いたり『衣羽』と書いたりするようです。
伝説では『袋羽』で、現在ある神社の額は『衣羽』になっています。
結城地方に同様の伝説がないか、また、ほろわ/袋羽神についての信仰・風習があるかについて、地図や文献でも調べているうちに、『ほろわ(ほろは)』について詳しく調査された方の論文(文献2、3)を見つけました。
それによると、『ほろわ(ほろは)神』は、東日本、特に東北から茨城にかけてかつて信仰されていた神様だったようです。
また茨城県内の『ほろわ(ほろは)』にまつわる神社等を詳細に調べられていて、結城市付近にはないようですが、筑波山の近く、つくば市北条にある八坂神社の境内社に、保呂羽(ほろは)神社があるとのこと。
川澄角平さんが結城に住んでいた時代(戦国時代終り~江戸時代初期)には、まだ『ほろわ神』信仰が続いていたのでしょう。
東日本の失われた民間信仰の痕跡が、遠く北陸の福井県の昔話に伝わっているのも面白いです!o(^o^)oワクワク。
【猫塚と袋羽/衣羽(ほろわ)神社】

さて、猫塚伝説の伝わる袋羽/衣羽(ほろわ)神社は、現在、福井市内にある神明神社という神社さんの境内に、合祀される形であります。
先月7月に、福井県福井市の方に行く機会がありました
 ので、猫塚伝説が伝わる袋羽(衣羽)神社がある、神明神社を訪れました(^^)v。
ので、猫塚伝説が伝わる袋羽(衣羽)神社がある、神明神社を訪れました(^^)v。
神明神社 拝殿
大きな神社さんです。

神社の境内に、3つの摂社を合祀したお社(合祭殿)があり、その中に袋羽神社もありました。
こちらの神明神社さんのHP(http://www.shinmei-jinja.jp/yurai/ )によると、ご祭神は『袋羽大神』とのこと。
合祀されたお社の額。
向かって一番左に『衣羽神社』の文字が。
中に入ると説明版がありました。
『袋羽神社(猫塚さん)
古くは「正保二年(一六四五年)三月吉祥日施主川澄角平興勝」の銘あり。天保・弘化の頃より庶民の信仰得て諸願成就の奇瑞あり。
「袋羽大神」は妻に化けた猫を退治した川澄角平が願を懸けた郷里・結城の産土、袋羽神を称えて建立したものと伝えられている。
現在も「猫塚さん」の名で親しまれ。子供の夜泣平癒に霊験があり、鰊(にしん)をそなえ、絵馬を掲げて子供の無事成長を祈願する人の参拝が絶えない。』
とのこと。
説明板の隣には、サンマを奉納するための立派な木製の箱もありました。
傍には同じく木製の板に書かれた
『お子様の夜泣き平癒お詣りの方は この中に「にしん」をお供えください。絵馬は社務所でお受けください』
の添え書きも。
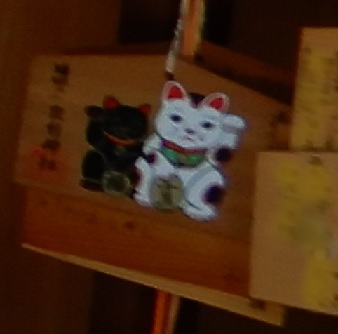
『招き猫』が描かれた絵馬もたくさん奉納されていました。
赤ちゃんの夜泣きなどに霊験あらたかとのことで、お参りしました(^^)
それにしても、
・退治された化け猫
・退治した(であろう)袋羽神
が習合して、
・『子供の夜泣きに効く』
という信仰に繋がった
その経緯にも、興味がわきます♪

そして現代では、化け猫ちゃんは、『招き猫』の絵柄になって絵馬に描かれている・・・というのも、日本の信仰っぽくて興味深いです
 。
。せっかく来ることが出来たので、お守り購入とご朱印も頂きたかったのですが、社務所に行って呼び鈴を鳴らしてもどなたも来られず
 、電車の時間も迫っていたので、そちらは泣く泣くあきらめました
、電車の時間も迫っていたので、そちらは泣く泣くあきらめました ・・・(拝殿でお祓いをされていたようなので、そちらでお忙しかったのかもしれません)。
・・・(拝殿でお祓いをされていたようなので、そちらでお忙しかったのかもしれません)。【養蚕と猫と信仰】
文献2,3 によると、『ほろわ』の語源はいろいろ考えられるようで、どういった神様だったかも不明のようですが、『ほろわ』に当てられた『袋羽』や『衣羽』という字に、繭を作り絹を生む『蚕』を連想しませんか?
私の勝手な想像ですが、養蚕業や織物が盛んな土地に伝わった『ほろわ神』は、養蚕の神様にもなって、『袋羽』や『衣羽』という字が当てられた・・・という可能性はありませんかねぇ(^^)。
(文献1でも触れられていますが、絹織物『羽二重』で有名な福井も、昔から絹織物で有名な地域です。)
そして茨城県結城市は、いわずと知れた絹織物の結城紬で有名。
一帯は養蚕業が古くから盛んでした。
養蚕業が盛んだった土地では、蚕の天敵の鼠を食べる猫が大事にされていたと聞きます。
なので、猫を祀るところもあるそうです。
なので、結城付近にも、蚕を(鼠から守る)猫を祀る祠やお社があってもよさそうなのですが、どうもない(今はない?)ようです。
結城地方に伝わる昔話に、猫の伝説はないかな?と、探していたら偶然にも結城に伝わる『ねこづか』伝説がありました!(文献4)
しかも、こちらも化け猫!

結城の『猫塚』伝説は、
お寺のお葬式で、遺体をくわえて逃げようとした黒猫の化け物を、和尚さんが斬りつける話。
逃げた化け猫が残した爪を集めて埋めた『ねこづか』が昔あったとのこと。
・・・残念ながら、福井の猫塚伝説とは直接関係はなさそうです・・・。
それにしても、羽二重の里の福井でも、結城紬の里の結城でも、お蚕さんを守るニャンコではなく、化け猫伝説なんですねぇ(^m^)。
・・・話が脱線しました(^^;)
養蚕に関する信仰に話を戻します。
結城からもよく見える筑波山の山麓には、絹織物の神様を祀る 蚕影山神社があります。
絹織物が一大産業だった明治時代から昭和の中ごろまでは、蚕影山神社には多くの参拝者が訪れて大変賑わったと聞きます。
そして、全国(特に関東甲信地区)には、この蚕影山神社を分祀した『蚕影神社』が建てられたそうです。
ちなみに以前書いた記事:
 → 東京・立川の『猫返し神社』と筑波山麓の関係!
→ 東京・立川の『猫返し神社』と筑波山麓の関係!にある、東京の立川市の蚕影神社は、阿豆佐味天(あずさみてん)神社、通称:立川水天宮の敷地の中にある境内社です。
もともとは直接『蚕―鼠―猫』繋がりはなく、現代になり偶然のきっかけで『猫の神様』的神社になっていますが、本来は蚕の神様を祀る蚕影神社です。
残念ながら・・・といいますか、総本社の蚕影山神社には、猫にまつわる伝説も信仰も伝わっていないのですが、こう見ていくと、日本の信仰って、とても面白いですね(^^)
【おまけ】
あと、もうひとつ、結城―福井の歴史的繋がりには、つくばも関わりがあります
 。
。先日のNHKの番組『歴史ヒストリア』でも、『戦国最弱(?)の大名にして『戦国の不死鳥』の異名を持つ』と紹介された、最近人気上昇中?!の小田氏治も、結城秀康とともに越前国に移り住み、そこで亡くなっています。
小田氏の居城だった小田城址歴史ひろばについても、以前書いた記事
 → 小田城跡歴史ひろば” の歩き方(入門編)
→ 小田城跡歴史ひろば” の歩き方(入門編)そして、福井の郷土料理と結城の郷土料理を融合させたみた 創作料理
 → 【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば(87)】 結城&福井の郷土食コラボ♪ すだれ麩ときゅうりの胡麻からし酢味噌和え
→ 【家庭で堪能!おいしい 茨城&つくば(87)】 結城&福井の郷土食コラボ♪ すだれ麩ときゅうりの胡麻からし酢味噌和えも良かったらお読み頂き、旅とグルメのご参考に(^^)v

***********************************************************************
【参考文献】
1.「妖怪ウォーカー」 村上健司 著 角川書店
2.「袋羽明神とホロハ塚」 徳原聡行 著 (茨城民俗学会誌 第26号 p.46-p.48)
3.「『ほろわ』考」 徳原聡行 著 (常総の歴史 第2号 p.82-p.90)
4.民話「ゆうき」 結城市教育委員会
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム










