2016年08月16日
茨城こんなもの見つけた♪(23) 常陸大宮の 珪化木 と メノウ
茨城こんなもの見つけた♪(23) 常陸大宮の 珪化木 と メノウ
以前(2013年12月30日)書いた記事、
→ 常陸国風土記1300年記念♪ 常陸国風土記の楽しみ方(後編 おでかけ編)
で、茨城県内で採取できる『パワーストーン』
の話を書きました。
既に約1300年前、奈良時代初めに編纂された『常陸国風土記』に、
『久慈郡』の項に、今でいう『メノウ』がとれる旨の記載があります 。
。
(当時の『久慈郡』は、現在の常陸大宮市の一部、常陸太田市の一部と日立市の一部が該当するようです。←詳細をご存じの方、ご教示頂けると嬉しいです)
 参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)
参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)
https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/index_fudoki.html
ちなみに現在の常陸大宮市は、江戸時代、火打石(=メノウ)の産地として有名でした。
火打石は水戸藩の特産品だったそうです 。
。
 火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです
火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです 。
。
参考:
 常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』
常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』
http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/sp/page/page000061.html
 常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)
常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)
http://www.hitachiomiya-furusatobunka.com/産物/瑪瑙-火打ち石/
常陸大宮市を流れる、玉川(久慈川支流)の河原では、メノウや、化石の珪化木が見られると聞いて、
いつか行ってみたいと思いながら、
なかなか行けないでいます。
・・・ところが、先日、県北の常陸大宮市ではありませんが、県央の笠間市の『石の百年館』に行く機会がありました。

石の百年館(写真右側の建物)
JR水戸線の『稲田駅』に隣接しています。
駅前の大きな石灯籠も、さすが稲田石(花崗岩)の産地!
稲田石のメッカの貫録、こじんまりしていながらも花崗岩製の美しく洗練された建物 。
。
 詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)
詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)
http://www.city.kasama.lg.jp/page/page006738.html
そこでなんと!
常陸大宮を流れる玉川(久慈川支流)の、珪化木と瑪瑙(めのう)が売られていました!
それも、めっちゃ、お手頃価格の500円♪
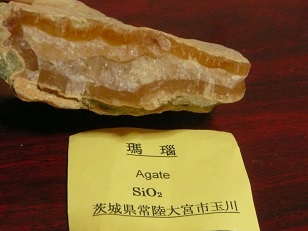
メノウ(瑪瑙)
真ん中の白い結晶部分を、赤っぽい部分がサンドイッチしています。
メノウは『アゲート』とも呼ばれるそうです。
主成分は二酸化珪素(SiO2)。
※そういえば、水晶はSiO2の結晶ですよね。結晶の仕方が違うだけで、成分的には同じなのね,,,φ(.. )

珪化木
化石の一種です。木だったということがよく伝わってきます。
石炭も『木の化石』ですが、珪化木もちょっと違うタイプの木の化石。
珪素(Si シリコン)を多く含む水分と圧力によって、長い年月を経て化石になったものだそう。
上のメノウの成分にもSiがありますね。やっぱり地層的に関係しているのかな? ←詳しい方ご教示下さい。
珪化木もいろんな色があるようですが、嬉しいことに白っぽいベージュの綺麗な珪化木が買えて嬉しい♪
もとは何の木だったんでしょう。
人類もまだいない、大昔の森林に思いを馳せます。
珪化木は、石炭と一緒に出てくることも多いそうです。
茨城県北には、常盤炭田など、石炭を含んだ地層が分布しているそうなので、こういった珪化木も出てきて、風化などで崩れて川を流れてきて、河原で採取出来たりするのでしょうか。
 参考: 茨城県北ジオサイト ホームページ
参考: 茨城県北ジオサイト ホームページ
http://www.ibaraki-geopark.com/
『パワーストーン』(=お守り)としての、めのう(アゲート)や珪化木については、インターネットで検索すると色々と効用が出てくるので、お好きな人は調べてみてください 。
。
どうせなら、外国産よりも国内産。
しかも地元 でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね
でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね (^^)v
(^^)v
以前(2013年12月30日)書いた記事、
→ 常陸国風土記1300年記念♪ 常陸国風土記の楽しみ方(後編 おでかけ編)
で、茨城県内で採取できる『パワーストーン』

の話を書きました。
既に約1300年前、奈良時代初めに編纂された『常陸国風土記』に、
『久慈郡』の項に、今でいう『メノウ』がとれる旨の記載があります
 。
。(当時の『久慈郡』は、現在の常陸大宮市の一部、常陸太田市の一部と日立市の一部が該当するようです。←詳細をご存じの方、ご教示頂けると嬉しいです)
 参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)
参考: 茨城県ホームページ(常陸国風土記)https://www.bunkajoho.pref.ibaraki.jp/index_fudoki.html
ちなみに現在の常陸大宮市は、江戸時代、火打石(=メノウ)の産地として有名でした。
火打石は水戸藩の特産品だったそうです
 。
。 火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです
火打ち石とは、摩擦による火花で火をおこすための道具。あと、よく時代劇などで、『あんた、気をつけて言ってらっしゃい』と、おかみさんがだんなさんを送り出す時に、魔よけとしてカチッカチッと打っている、あれです 。
。参考:
 常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』
常陸大宮市ホームページ 『歴史民俗資料館 山方町』http://www.city.hitachiomiya.lg.jp/sp/page/page000061.html
 常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)
常陸大宮市のたからもの > 産物 >瑪瑙(火打ち石)http://www.hitachiomiya-furusatobunka.com/産物/瑪瑙-火打ち石/
常陸大宮市を流れる、玉川(久慈川支流)の河原では、メノウや、化石の珪化木が見られると聞いて、
いつか行ってみたいと思いながら、
なかなか行けないでいます。
・・・ところが、先日、県北の常陸大宮市ではありませんが、県央の笠間市の『石の百年館』に行く機会がありました。

石の百年館(写真右側の建物)
JR水戸線の『稲田駅』に隣接しています。
駅前の大きな石灯籠も、さすが稲田石(花崗岩)の産地!
稲田石のメッカの貫録、こじんまりしていながらも花崗岩製の美しく洗練された建物
 。
。 詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)
詳細 笠間市公式ホームぺージ > 観光 > 学ぶ > 石の百年館 > 石の百年館(トップページ)http://www.city.kasama.lg.jp/page/page006738.html
そこでなんと!
常陸大宮を流れる玉川(久慈川支流)の、珪化木と瑪瑙(めのう)が売られていました!

それも、めっちゃ、お手頃価格の500円♪

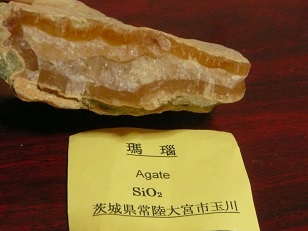
メノウ(瑪瑙)
真ん中の白い結晶部分を、赤っぽい部分がサンドイッチしています。
メノウは『アゲート』とも呼ばれるそうです。
主成分は二酸化珪素(SiO2)。
※そういえば、水晶はSiO2の結晶ですよね。結晶の仕方が違うだけで、成分的には同じなのね,,,φ(.. )

珪化木
化石の一種です。木だったということがよく伝わってきます。
石炭も『木の化石』ですが、珪化木もちょっと違うタイプの木の化石。
珪素(Si シリコン)を多く含む水分と圧力によって、長い年月を経て化石になったものだそう。
上のメノウの成分にもSiがありますね。やっぱり地層的に関係しているのかな? ←詳しい方ご教示下さい。
珪化木もいろんな色があるようですが、嬉しいことに白っぽいベージュの綺麗な珪化木が買えて嬉しい♪
もとは何の木だったんでしょう。
人類もまだいない、大昔の森林に思いを馳せます。
珪化木は、石炭と一緒に出てくることも多いそうです。
茨城県北には、常盤炭田など、石炭を含んだ地層が分布しているそうなので、こういった珪化木も出てきて、風化などで崩れて川を流れてきて、河原で採取出来たりするのでしょうか。
 参考: 茨城県北ジオサイト ホームページ
参考: 茨城県北ジオサイト ホームページhttp://www.ibaraki-geopark.com/
『パワーストーン』(=お守り)としての、めのう(アゲート)や珪化木については、インターネットで検索すると色々と効用が出てくるので、お好きな人は調べてみてください
 。
。どうせなら、外国産よりも国内産。
しかも地元
 でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね
でとれたパワーストーンの方が、お守りとして威力ありそう…ですよね (^^)v
(^^)v※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム









