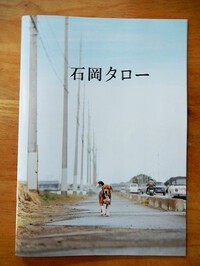2021年12月27日
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《後編》
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《後編》
茨城3つの養蚕信仰の聖地について、じっくり調べて考えていくシリーズ。
文献を参照しつつ、取り組んでいきますので、お付き合い下さい
前回までの話
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(1)
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(1)
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(2) ~ 蚕伝来の伝説と「豊浦」
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(2) ~ 蚕伝来の伝説と「豊浦」
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(3) ~ うつぼ舟・常陸国とゆら・筑波山・富士山
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(3) ~ うつぼ舟・常陸国とゆら・筑波山・富士山
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(4) ~金色姫譚と富士山信仰 及び 金色姫譚の誕生仮説
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(4) ~金色姫譚と富士山信仰 及び 金色姫譚の誕生仮説
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》
物的証拠も記録もないので、伝承や地形・状況からの類推になりますが、妄想の翼を広げつつも、なるべく説得力ある考察を心がけています 。
。
※ なお、この記事に出てくる『蠶』は『蚕』の旧字、『䗝』は、『蚕』の異体字です。
また当記事では、神社名の『蠶養神社』は、同神社の扁額の記載に従っています。多くの参考文献では『蚕養神社』となっていますが、当記事では旧字の『蠶養』と記載します。
さて今回は日立市川尻地区にある蠶養神社の後編、蠶養神社についての考察のまとめです。

(写真は、蠶養神社。2020年8月撮影)
【現在の蠶養神社について文献から分かること(客観的事実)】
前回 (茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》)では、日立市川尻の蠶養神社の歴史について書きました。
常陸国三蚕神社の他の2つの神社に比べ、地味なのに、江戸時代、怒濤の(?)歴史を経て、今に至るのが分かり、びっくりです。
そして、現時点で各資料から分かることは、以下の①~⑥の6つだと云えます(文献1、2、8、10、11)。

① 旧川尻村の『津明神』=(~明治34年まで)於岐津説神社 =(明治34年~現在)蠶養神社
② 元禄五年(西暦1692年)の頃、一度取り潰しが決まった川尻の『津明神』が、逆に神主も置かれて存続することになった。
これは、地元の漁村民はこの明神を『おきぢさま』と呼んで大切にし、雉子を『おきぢさま』(またはそのお使い?)と見なしていたのか、雉子が鳴くと『おきぢさまの御鳴なさる』と言っていたとのことで、地元の人達からとても崇敬されていたため。
③ 元禄年中1688年~1704年の頃には、『(神の下に虫)養濱神虫神石御命にてこれ全く神虫種神躰に等し』、
『全く日本最初 蟲の初まりと成こと今に年々歳々…』
という信仰があった模様。
④ 寛政十年(1798年)に水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝が撰した縁起文で、『蠶影大明神』の名 及び『蠶養嶺地主神』の名が出る。
これは、宝永五年(西暦1708年)以降に書かれたであろう『常陸國蠶養嶺略縁起』
(『常陸國梁津庄豊浦湊多珂郡河尻村 日本最初蠶養嶺 大神主 大都權之太輔』)
が元であると思われる。
⑤ 同じく寛政十年(1798年)に水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝が撰した縁起文で、『豊浦湊』という地名とヤマトタケル(大和武尊)との関わりが、記されている。
⑥ 『河尻村日本最初蠶養嶺 大神主 大都權之太輔による縁起にも、水戸彰考館の青山延彝による縁起文にも、『金色姫』については言及無し。
【現在の蠶養神社について考えられること(私見的考察)】
以上のことを発展させると、 旧川尻村の『津明神』=(~明治34年まで)於岐津説神社 =(明治34年~現在)蚕養神社 については、
以下の(A)(B)(C)(D)のことが云えるのではないかと考えます。
(A) 『おきぢさま』と村漁民から深く崇敬されていた。それゆえ取り壊されず、あらたに祭祀者が付けられた。

(蠶養神社の境内付近から、小貝浜とは反対側の、北のウミウ捕獲場のある方向を望む 2020年8月撮影)
⇩
●漁業に携わる人からの崇敬があるということは、元々は漁業の神・豊漁の神・航海安全の神だったのではないか?
●お社のある位置も海に突き出た丘の上にあって、漁業・航海安全の祈願をされていたというのは理解しやすい。
(B) 大神主 大都權之太輔による縁起(文献11)によると、ある時(時代不明)、この地の沖(東方沖?)に蚕?繭?の形をしたものが 浮いているのが発見され、それを『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』名付けて、おきぢさまの境内に安置された。
特に 元禄年中1688年~1704年の頃から、『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』という名の神として崇められ、 一時水戸藩により信仰を禁止されるが、それでも復活して段々信仰が広まった模様。
⇩
●その当時、当地やその周辺では養蚕が行わていて、養蚕の神として流行神のように『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』信仰が
広まったと考えられる。
(C) 『豊浦湊』『大和武尊』の名は、水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝の縁起文に出てくる。
大和武尊が『豊浦湊』から上陸し、この社で祈願したら、戦わずして蝦夷に勝てたということでこの社に寄進をしたというエピソードあり。
このヤマトタケル(大和武尊)の伝説は古事記・日本書記・常陸国風土記には見られない(文献9)。
いつごろから語られるようになっていたのかは不明。
⇩
●ヤマトタケルがこの土地の神に祈ったら『戦わずに』蝦夷を平らげることが出来たというエピソードは、蝦夷の人にシンパシーを感じているこの土地の人々、そして征服・平定しにきた大和の政権に忸怩たる想いを持つ人々が、隠れたその思いを語り継いできた伝説のように感じる。
(D) 金色姫譚は全く触れられていない。
子貝浜の小さな赤い巻貝や綺麗な石を蚕のお守りとする信仰(文献3、4、5、7)はいつから始まったか不明。
金色姫の赤い巻貝の首飾りの話(文献7 及び境内の掲示板)も、いつごろに生まれたか不明。
⇩
●江戸時代前期の頃は、金色姫伝説はこの地に伝わってなかったのか?
●もしくはこの地には金色姫譚は伝わっていたが、川尻の津明神(於岐津説神社)とは違う系統の伝説だったので、神社の公式な縁起とされなかったので 記録されなかったか?
●それがいつしか川尻の津明神(於岐津説神社)の信仰と混淆していったか?
【現在の蠶養神社と金色姫譚との関係についての仮説】
室町後期の永禄元年(西暦1558年)に京都で記録された『戒言』の『常陸国とよら』とのミッシングリングは埋まりませんが、 もし常陸国の中で最初にこの地に『原 金色姫譚』が伝わったとした場合 、私は以下の仮説が言えるように思っています。
【仮説】
① 日立市の川尻地区・蠶養神社付近には、古くから語られたローカルなヤマトタケル伝説とそれにちなむ『豊浦湊』という地があった。
② 複数の系統・技術・言い伝えを持つ織物技術のグループが古くから住んでいたと考えられる。
茨城県北あたりは、もともと織物の神を祀る古い神社が複数ある。
静神社、長旗部神社、大甕神社など、それぞれ違う系統の織物の神と思われる。
③ 船の遭難か何かで、豊浦港付近に、従来から住んでいた②のグループとは別系統の人々がこの地に流れ着き、養蚕技術・蚕種や独自の伝説をこの地に伝えた。
④ 上記③の事情で伝説と手法等が伝わった痕跡が、金色姫伝説ではないか。この地の人々はその伝説と養蚕・織物の手法を細々と伝えていたのかもしれない。
また赤い貝の首飾りの話など、いわゆるシャーマン的存在を感じる。
⑤ またこの辺りは阿武隈山系が海の近くまで迫っている。阿武隈山系で修行したり移動する修験道や山岳修行者が古くからいた。
この山岳修行者が、金色姫伝説や養蚕、織物技術的なものを、別の土地に伝えたのではないか?
※ この山岳修行者の介入の可能性については、前回の記事
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》
も、ご参照下さい。
この地に伝わる金色姫伝説には、筑波山ほんどう仙人も富士山かぐや姫も出てこない。
これは、本来の伝説は金色姫が亡くなるところまでで、その後、山岳宗教者(修験者など)がこの伝説を取り込み、まず阿武隈山系南端の筑波山系の山岳宗教者が金色姫譚を知って『筑波山のほんどう仙人』の話を作って付け加え、筑波山方面に金色姫譚を伝えたか?
その後、富士山信仰の山岳宗教者が、関東布教の折に、ほんどう仙人の話も含めた金色姫譚を知り、それに『富士山のかぐや姫』の話を作ってさらに付け加え、布教の際にこの話を広く広めて京都まで伝わり、1500年代、京都まで伝わり、『戒言』として記録されたか?
⑥ 川尻の津明神(おきつせ神社)は、当初は養蚕とは関係なく、豊漁と航海安全の神だった。
江戸時代の頃(元禄年中(1688年~1704年))、川尻の沖に『蚕形』のものがあるのを見つけ『蠶養大明神 蠶養嶺地主神』と名付けて川尻の津明神境内か(もしくはその近く?)に祀った人がいた。

(蠶影神社の境内の先から海を望む。看板には大変おおまかなこの辺りの地図。地図としてはもう少し情報が欲しいところ。2020年8月撮影)
おりしも養蚕が奨励されてきつつある時、守り神として流行神の様に信仰がひろまり、淫祀邪教を徹底的に取り締まった水戸藩(水戸光圀)が禁止したが、それでも信仰され、寛政十年(1798年)に水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝が撰した縁起文には、それらの神名(『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』『蠶養大明神 蠶養嶺地主神』)が記されるようになった。
⑦ 同じく江戸中期ごろになると、養蚕が各地で行われるようになり、育てるのに大変な蚕を守るための神仏への信仰もまた求められるようになった。その需要にいち早く対応し、布教活動に力を入れたのが、神栖の星福寺(蚕霊神社)と、筑波山麓の桑林寺(蚕影山神社)。星福寺は、特に衣襲(きぬがさ)明神を蚕の神仏として布教し、桑林寺は金色姫を蚕影山明神と同じ神として布教した。衣襲明神(絹笠明神とも)は群馬の方で特に信仰され、蚕影山明神(金色姫)は東京・神奈川・山梨方面で信仰された。
どちらも、利根川・鬼怒川・桜川などの水運の近くで、布教のための移動もしやすく、また信者も詣でやすい土地だったと思われる。
しかも、星福寺は、鹿島・香取・息栖の東国三社詣での地に近く、桑林寺(蚕影山神社)も、筑波山の知足院中禅寺(現在の筑波山神社)に近い。信者が東国三社詣でのついでに詣でやすい。
それに比べ、日立・川尻の『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』『蠶養大明神 蠶養嶺地主神』は、桑原寺(蚕影山神社)や星福寺(蚕霊神社)のような強力な布教活動はしなかった上に、東国三社や筑波山中禅寺のような有名寺が近くにない。また他の土地(内陸』を自由に移動できる水運の盛んな川も近くになく、地の利に乏しい。
水戸藩による徹底した宗教政策の影響も大きかっただろう。
そういった条件が重なり、隣の福島までぐらいしか信仰が広がりにくく、そのため知名度も低いのではないか。
⑧ 金色姫伝説は本来の津明神の信仰とは関係なかったので、津明神(於岐津説神社)の縁起文、すなわち、宝永五年(西暦1708年)以降に書かれたであろう『常陸國蠶養嶺略縁起』(『常陸國梁津庄豊浦湊多珂郡河尻村 日本最初蠶養嶺 大神主 大都權之太輔』)にも、寛政十年(西暦1798年)の水戸彰考館編集神道司経青山延彝による縁起文にも触れられていないのではないか。
しかし、この地で元々細々と伝わっていた金色姫伝説は、庶民の中で津明神の近くで祀られた、蚕形の御神体の神と同じ養蚕の神として結びつき、明治以降養蚕が盛んになるにつれてそちらが有名になり、『津明神=於岐津説神社』から、明治時代になり『蠶養神社』と社名も変わり、さらに大正時代には祭神も追加されて現在の祭神3柱になったか?
【蠶養神社の和賛に謳われる、金色姫譚にまつわる地名】
ちなみに、文献7に、昭和2年に福島県の相沢さんという方が作ったという『かひこ礼讃』が掲載されています。
大変長い和讃ですが、その中に、川尻・蠶養神社周辺の、金色姫譚にまつわるらしい地名が数多く出てきます。
それを、順に並べると、
イワヒ山、コカヒがハマ、蚕島、そだて島、かがて姫島、かくれ磯、ぢい磯、ばあ磯、めをと磯、袖ケ浦、三宝磯、経が島、タテ山、ビヨウブ岩、ボダイ山、マユ磯、蝶島、鍋島、イビラ島、経繰(ヘグリ)の磯、
ザグリ穴、船橋、イト磯、タカラ磯、アヤ磯、錦島、コロモ磯、太夫がヤカタ、外記ヤシキ、赤見台、あまつシミツの井戸、トヨラ潟、えびすの穴、鯛の磯、ベンテン崎、ホテイ岩、ダイコク島、ビシヤモン堂、コカヒがみね
・・・最後のあたりは七福神関係(^^;)ですね 。
。
しかし逆に、金色姫譚と養蚕・織物にまつわる名がつけられた地名、そしてめでたい七福神との混淆が、民衆の生々しい信仰と願いを伝えていると感じます。
現在はそれぞれがどこに該当するのか分からないようですが、少なくともそう呼ばれた地名が当時の頃まではあったということでしょう。
それにしても、この『こかひ礼賛』の名所紹介の箇所を歌うと、この辺りの海岸線や、小島、岩、浜辺の様子が目に浮かぶようです 。
。
(文献7の『筑波歴史散歩』(宮本宣一 著)に、筑波山麓から遠く離れた、貴重な蠶養神社の『かひこ礼讃』が全文記載されている
のは、素晴らしいと思いました。著者は、蚕影山神社の『蚕影山和讃』を元にした例として紹介していますが)
以上述べてきたことを考えると、実はこの日立市川尻地区が、『常陸国における金色姫譚の始まりの地』
の可能性が一番高いのではないかと、私は考えています 。
。
【ジオから見た蠶養神社の信仰】
さてこの地での金色姫伝説については、この土地特有のジオも関わっていると思います。
つまり、この日立市川尻地区の周辺の、海洋生物の生態、地形、地質、海流の条件が見事に重なって、蚕のお守り=サンショウガイや綺麗な小石という民間信仰が生まれた言えるでしょう。
(1) 砂浜の貝殻:鮮やかな赤色の小さな巻貝がある。
昔は浜辺が赤くなるほど、サンショウガイの貝殻があったと云います(文献3、4、6)

その赤い小さな巻貝は『サンショウガイ』
サンショウガイはサザエ科の微小な巻貝。
 参考サイト:微小貝さがしサポートデータベース
参考サイト:微小貝さがしサポートデータベース
地元の伝承(文献3、4、6)では『蚕生貝』という字を当てられ、蚕のお守りにするとされたとのこと。
 参考サイト:
参考サイト:
日立市HP 金色姫伝説、サンショウガイ
もしかすると、
『赤い』サンショウガイ と 『白い』蚕 ⇒ 赤と白の組み合わせに 『めでたい』 ⇒ 『良い生育』
を、願ったのかもしれませんね 。
。
(2) 砂浜の砂利:きれいな小石。常陸国風土記にも、「碁石」など綺麗な小石の浜があると書かれている。
これも蚕のお守りにするとされたと云います(文献6)。

これは、茨城県北の山で産出する、めのうや玉髄などが川から海に流れていき、きれいな小石の砂利となっているためです。
茨城県北、奥久慈の山はメノウや玉髄の産地です 。
。
 久慈川上流のメノウについては、以前書いた記事もご参照下さい
久慈川上流のメノウについては、以前書いた記事もご参照下さい
→ 茨城こんなもの見つけた♪(23) 常陸大宮の 珪化木 と メノウ
久慈川・十王川水系(久慈川 · 里川 · 茂宮川 · 入四間川 · 落見川、十王川)が、山から風化等で崩れてきたメノウや玉髄を運び、 更にそれらが細かい砂利となって、この辺りの美しい海岸の砂利を作っているのですね。
(3)海流:この土地は外洋に面した土地。

(小貝浜の南に隣接する川尻海水浴場 2020年8月撮影)
そして、この茨城県沖は、黒潮と親潮がぶつかるエリア。
海産物も豊富だが、遠くから流されてくる漂着物も多く、昔から様々なものが流れ着きました。
例えば、文献1では、漂流していた琉球船が流れ着いた記録も記されています。
ご神体とされていた『蚕形』の石(文献11)に書かれた縁起書には、この浦の沖で蚕形のもの(石?)が浮いているのが発見され、それを 上子山(現在の蚕養神社のある高台か?)に安置して、『䗝養濱神虫神石御命』『蚕養大明神 蚕養嶺地主神』『蚕養大明神』としたとあります。
※『䗝』 (『神』の下に『虫』、蚕の異体字)
またその『蚕形』の石が発見された翌日に、『従者のように小石が沢山 流れ着いた』という話も、後から海流に乗って次々に漂着した軽石を思わせます。
海流の関係から、例えば伊豆諸島の火山や海底火山が噴火したら、噴出物の軽石などが流れ着く可能性は大いに考えられます。
(今年2021年の8月小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」噴火し、海流に乗った大量のよる軽石が、10月には奄美・沖縄方面に大量に漂着し、11月には千葉県の海岸にも漂着が確認されたニュースの記憶が新しいです)
このようなジオ的な目で見ると、この土地に伝わる信仰についても、また違った風景が見えてきますね。
【おまけ】 つくばにある『蚕養神社』

さて、つくば市上郷、小貝川のほとりにある金村別雷神社。
(写真は金村別雷神社。2021年10月撮影)
その金村別雷神社の境内に、『蚕養神社』があります(※)。
すぐ近く、筑波山麓の蚕影山神社(蚕影神社)でなく、『蚕養神社』なのです!
(※)つくば市内に蚕養神社があるのは、(当時)神栖町歴史民俗資料館が発行した 『第19回企画展 蚕物語 ~天の虫・糸の虫~』(文献 13) の 『茨城県内の養蚕・機織りに関する神社と地名』の地図で見つけ、具体的にどこにあるのか、同資料館に問い合わせたところ、金村別雷神社の境内にあるとご教示頂きました。
神栖市歴史民俗資料館の職員の方、ありがとうございました。

金村別雷神社の本殿の裏手側、複数の祠が並ぶ中に、蚕養神社があります。
(こちらの祠の扁額には『蚕養神社』となってますので、当ブログでもこちらの神社は旧字を使った『蠶養』でなく『蚕養』と書きます)
お詣りされる方が多いのか、小さなお賽銭箱もあり、お酒も奉納されています 。
。
(2021年10月撮影)
上郷地区(旧 豊里町)は、昔は養蚕が盛んな場所でした。
そして先ごろ廃校になってしまいましたが、県立上郷高等学校の前身は、『上郷養蚕高等学校』でした(文献14)。
そういった土地だったので、『蚕養神社』の祠が奉られ、信仰されてきたのでしょう。

しかしなぜ、(筑波山に隣接する)蚕影山に比較的近いこの地に、『蚕影山神社/蚕影神社』ではなくて、『蚕養神社』の祠が建立され、信仰されてきたのでしょうか。
日立・川尻の蚕養神社から分霊したものなのか?はたまた偶然の名前の一致なのか?
神社の方にここの蚕養神社の祠について尋ねましたが、『この辺りにあった小さな祠をまとめたものです』ということで、
詳しいことは分からないとのことでした。
もしご存じの方がおられたら、ご教示下さい。
次回からは、神栖の星福寺/蚕霊神社 について考えていきます。
続きます。
→ 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(6)~神栖市 蠶霊神社・星福寺《前編》
************************
【参考文献】
1. 『常陸多賀郡史(復刻版)』 千秋社
2. 『新修 日立市史 上巻』 日立市史編さん委員会 日立市
3. 『ひたち地方の伝説ー郷愁の伝承誌ー』 柴田勇一郎 著 日立市民文化事業団
4. 『日立の伝説』 柴田勇一郎 著 筑波書林 (※ 『ひたち地方の伝説ー郷愁の伝承誌ー』 と同じ内容)
5. 『蚕 絹糸を吐く虫と日本人』 畑中章宏 著 晶文社
6. 『水戸黄門の遊跡 -日立地方の巻-』 鈴木彰 著 崙書房
7. 『筑波歴史散歩』 宮本宣一 著 日経事業出版センター
8. 『茨城県神社誌』 茨城県神社誌編纂委員会 茨城県神社庁
9. 『ヤマトタケルと常陸国風土記』 黒澤彰哉 著 茨城新聞社
10. 『日立市史』 日立市役所 常陸書房
11. 『養蠶の神々-蚕神信仰の民俗-』 阪本英一 著 群馬県文化事業振興会
12. 『地球再発見 いばらき自然ものがたり』 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 編 茨城新聞社
いばらきの自然
13. 『第19回企画展 蚕物語 ~天の虫・糸の虫~』 神栖町歴史民俗資料館
14. 『豊里町の歴史』 豊里町史編纂委員会 豊里町
【参考サイト】
微小貝さがしサポートデータベース
http://bishogai-sagashi.jp/search/block.php
http://bishogai-sagashi.jp/sp/
日立市HP 金色姫伝説、サンショウガイ
https://www.city.hitachi.lg.jp/citypromotion/hitachikaze/boasts/view/p092362.html
茨城3つの養蚕信仰の聖地について、じっくり調べて考えていくシリーズ。
文献を参照しつつ、取り組んでいきますので、お付き合い下さい

前回までの話
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(1)
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(1) 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(2) ~ 蚕伝来の伝説と「豊浦」
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(2) ~ 蚕伝来の伝説と「豊浦」 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(3) ~ うつぼ舟・常陸国とゆら・筑波山・富士山
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(3) ~ うつぼ舟・常陸国とゆら・筑波山・富士山 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(4) ~金色姫譚と富士山信仰 及び 金色姫譚の誕生仮説
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(4) ~金色姫譚と富士山信仰 及び 金色姫譚の誕生仮説 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》物的証拠も記録もないので、伝承や地形・状況からの類推になりますが、妄想の翼を広げつつも、なるべく説得力ある考察を心がけています
 。
。※ なお、この記事に出てくる『蠶』は『蚕』の旧字、『䗝』は、『蚕』の異体字です。
また当記事では、神社名の『蠶養神社』は、同神社の扁額の記載に従っています。多くの参考文献では『蚕養神社』となっていますが、当記事では旧字の『蠶養』と記載します。
さて今回は日立市川尻地区にある蠶養神社の後編、蠶養神社についての考察のまとめです。

(写真は、蠶養神社。2020年8月撮影)
【現在の蠶養神社について文献から分かること(客観的事実)】
前回 (茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》)では、日立市川尻の蠶養神社の歴史について書きました。
常陸国三蚕神社の他の2つの神社に比べ、地味なのに、江戸時代、怒濤の(?)歴史を経て、今に至るのが分かり、びっくりです。
そして、現時点で各資料から分かることは、以下の①~⑥の6つだと云えます(文献1、2、8、10、11)。

① 旧川尻村の『津明神』=(~明治34年まで)於岐津説神社 =(明治34年~現在)蠶養神社
② 元禄五年(西暦1692年)の頃、一度取り潰しが決まった川尻の『津明神』が、逆に神主も置かれて存続することになった。
これは、地元の漁村民はこの明神を『おきぢさま』と呼んで大切にし、雉子を『おきぢさま』(またはそのお使い?)と見なしていたのか、雉子が鳴くと『おきぢさまの御鳴なさる』と言っていたとのことで、地元の人達からとても崇敬されていたため。
③ 元禄年中1688年~1704年の頃には、『(神の下に虫)養濱神虫神石御命にてこれ全く神虫種神躰に等し』、
『全く日本最初 蟲の初まりと成こと今に年々歳々…』
という信仰があった模様。
④ 寛政十年(1798年)に水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝が撰した縁起文で、『蠶影大明神』の名 及び『蠶養嶺地主神』の名が出る。
これは、宝永五年(西暦1708年)以降に書かれたであろう『常陸國蠶養嶺略縁起』
(『常陸國梁津庄豊浦湊多珂郡河尻村 日本最初蠶養嶺 大神主 大都權之太輔』)
が元であると思われる。
⑤ 同じく寛政十年(1798年)に水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝が撰した縁起文で、『豊浦湊』という地名とヤマトタケル(大和武尊)との関わりが、記されている。
⑥ 『河尻村日本最初蠶養嶺 大神主 大都權之太輔による縁起にも、水戸彰考館の青山延彝による縁起文にも、『金色姫』については言及無し。
【現在の蠶養神社について考えられること(私見的考察)】
以上のことを発展させると、 旧川尻村の『津明神』=(~明治34年まで)於岐津説神社 =(明治34年~現在)蚕養神社 については、
以下の(A)(B)(C)(D)のことが云えるのではないかと考えます。
(A) 『おきぢさま』と村漁民から深く崇敬されていた。それゆえ取り壊されず、あらたに祭祀者が付けられた。

(蠶養神社の境内付近から、小貝浜とは反対側の、北のウミウ捕獲場のある方向を望む 2020年8月撮影)
⇩
●漁業に携わる人からの崇敬があるということは、元々は漁業の神・豊漁の神・航海安全の神だったのではないか?
●お社のある位置も海に突き出た丘の上にあって、漁業・航海安全の祈願をされていたというのは理解しやすい。
(B) 大神主 大都權之太輔による縁起(文献11)によると、ある時(時代不明)、この地の沖(東方沖?)に蚕?繭?の形をしたものが 浮いているのが発見され、それを『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』名付けて、おきぢさまの境内に安置された。
特に 元禄年中1688年~1704年の頃から、『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』という名の神として崇められ、 一時水戸藩により信仰を禁止されるが、それでも復活して段々信仰が広まった模様。
⇩
●その当時、当地やその周辺では養蚕が行わていて、養蚕の神として流行神のように『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』信仰が
広まったと考えられる。
(C) 『豊浦湊』『大和武尊』の名は、水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝の縁起文に出てくる。
大和武尊が『豊浦湊』から上陸し、この社で祈願したら、戦わずして蝦夷に勝てたということでこの社に寄進をしたというエピソードあり。
このヤマトタケル(大和武尊)の伝説は古事記・日本書記・常陸国風土記には見られない(文献9)。
いつごろから語られるようになっていたのかは不明。
⇩
●ヤマトタケルがこの土地の神に祈ったら『戦わずに』蝦夷を平らげることが出来たというエピソードは、蝦夷の人にシンパシーを感じているこの土地の人々、そして征服・平定しにきた大和の政権に忸怩たる想いを持つ人々が、隠れたその思いを語り継いできた伝説のように感じる。
(D) 金色姫譚は全く触れられていない。
子貝浜の小さな赤い巻貝や綺麗な石を蚕のお守りとする信仰(文献3、4、5、7)はいつから始まったか不明。
金色姫の赤い巻貝の首飾りの話(文献7 及び境内の掲示板)も、いつごろに生まれたか不明。
⇩
●江戸時代前期の頃は、金色姫伝説はこの地に伝わってなかったのか?
●もしくはこの地には金色姫譚は伝わっていたが、川尻の津明神(於岐津説神社)とは違う系統の伝説だったので、神社の公式な縁起とされなかったので 記録されなかったか?
●それがいつしか川尻の津明神(於岐津説神社)の信仰と混淆していったか?
【現在の蠶養神社と金色姫譚との関係についての仮説】
室町後期の永禄元年(西暦1558年)に京都で記録された『戒言』の『常陸国とよら』とのミッシングリングは埋まりませんが、 もし常陸国の中で最初にこの地に『原 金色姫譚』が伝わったとした場合 、私は以下の仮説が言えるように思っています。
【仮説】
① 日立市の川尻地区・蠶養神社付近には、古くから語られたローカルなヤマトタケル伝説とそれにちなむ『豊浦湊』という地があった。
② 複数の系統・技術・言い伝えを持つ織物技術のグループが古くから住んでいたと考えられる。
茨城県北あたりは、もともと織物の神を祀る古い神社が複数ある。
静神社、長旗部神社、大甕神社など、それぞれ違う系統の織物の神と思われる。
③ 船の遭難か何かで、豊浦港付近に、従来から住んでいた②のグループとは別系統の人々がこの地に流れ着き、養蚕技術・蚕種や独自の伝説をこの地に伝えた。
④ 上記③の事情で伝説と手法等が伝わった痕跡が、金色姫伝説ではないか。この地の人々はその伝説と養蚕・織物の手法を細々と伝えていたのかもしれない。
また赤い貝の首飾りの話など、いわゆるシャーマン的存在を感じる。
⑤ またこの辺りは阿武隈山系が海の近くまで迫っている。阿武隈山系で修行したり移動する修験道や山岳修行者が古くからいた。
この山岳修行者が、金色姫伝説や養蚕、織物技術的なものを、別の土地に伝えたのではないか?
※ この山岳修行者の介入の可能性については、前回の記事
 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(5) ~ 日立市 蠶養神社 《前編》も、ご参照下さい。
この地に伝わる金色姫伝説には、筑波山ほんどう仙人も富士山かぐや姫も出てこない。
これは、本来の伝説は金色姫が亡くなるところまでで、その後、山岳宗教者(修験者など)がこの伝説を取り込み、まず阿武隈山系南端の筑波山系の山岳宗教者が金色姫譚を知って『筑波山のほんどう仙人』の話を作って付け加え、筑波山方面に金色姫譚を伝えたか?
その後、富士山信仰の山岳宗教者が、関東布教の折に、ほんどう仙人の話も含めた金色姫譚を知り、それに『富士山のかぐや姫』の話を作ってさらに付け加え、布教の際にこの話を広く広めて京都まで伝わり、1500年代、京都まで伝わり、『戒言』として記録されたか?
⑥ 川尻の津明神(おきつせ神社)は、当初は養蚕とは関係なく、豊漁と航海安全の神だった。
江戸時代の頃(元禄年中(1688年~1704年))、川尻の沖に『蚕形』のものがあるのを見つけ『蠶養大明神 蠶養嶺地主神』と名付けて川尻の津明神境内か(もしくはその近く?)に祀った人がいた。

(蠶影神社の境内の先から海を望む。看板には大変おおまかなこの辺りの地図。地図としてはもう少し情報が欲しいところ。2020年8月撮影)
おりしも養蚕が奨励されてきつつある時、守り神として流行神の様に信仰がひろまり、淫祀邪教を徹底的に取り締まった水戸藩(水戸光圀)が禁止したが、それでも信仰され、寛政十年(1798年)に水戸彰考館の編集神道司経の青山延彝が撰した縁起文には、それらの神名(『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』『蠶養大明神 蠶養嶺地主神』)が記されるようになった。
⑦ 同じく江戸中期ごろになると、養蚕が各地で行われるようになり、育てるのに大変な蚕を守るための神仏への信仰もまた求められるようになった。その需要にいち早く対応し、布教活動に力を入れたのが、神栖の星福寺(蚕霊神社)と、筑波山麓の桑林寺(蚕影山神社)。星福寺は、特に衣襲(きぬがさ)明神を蚕の神仏として布教し、桑林寺は金色姫を蚕影山明神と同じ神として布教した。衣襲明神(絹笠明神とも)は群馬の方で特に信仰され、蚕影山明神(金色姫)は東京・神奈川・山梨方面で信仰された。
どちらも、利根川・鬼怒川・桜川などの水運の近くで、布教のための移動もしやすく、また信者も詣でやすい土地だったと思われる。
しかも、星福寺は、鹿島・香取・息栖の東国三社詣での地に近く、桑林寺(蚕影山神社)も、筑波山の知足院中禅寺(現在の筑波山神社)に近い。信者が東国三社詣でのついでに詣でやすい。
それに比べ、日立・川尻の『(神の下に虫)養濱神虫神石御命』『蠶養大明神 蠶養嶺地主神』は、桑原寺(蚕影山神社)や星福寺(蚕霊神社)のような強力な布教活動はしなかった上に、東国三社や筑波山中禅寺のような有名寺が近くにない。また他の土地(内陸』を自由に移動できる水運の盛んな川も近くになく、地の利に乏しい。
水戸藩による徹底した宗教政策の影響も大きかっただろう。
そういった条件が重なり、隣の福島までぐらいしか信仰が広がりにくく、そのため知名度も低いのではないか。
⑧ 金色姫伝説は本来の津明神の信仰とは関係なかったので、津明神(於岐津説神社)の縁起文、すなわち、宝永五年(西暦1708年)以降に書かれたであろう『常陸國蠶養嶺略縁起』(『常陸國梁津庄豊浦湊多珂郡河尻村 日本最初蠶養嶺 大神主 大都權之太輔』)にも、寛政十年(西暦1798年)の水戸彰考館編集神道司経青山延彝による縁起文にも触れられていないのではないか。
しかし、この地で元々細々と伝わっていた金色姫伝説は、庶民の中で津明神の近くで祀られた、蚕形の御神体の神と同じ養蚕の神として結びつき、明治以降養蚕が盛んになるにつれてそちらが有名になり、『津明神=於岐津説神社』から、明治時代になり『蠶養神社』と社名も変わり、さらに大正時代には祭神も追加されて現在の祭神3柱になったか?
【蠶養神社の和賛に謳われる、金色姫譚にまつわる地名】
ちなみに、文献7に、昭和2年に福島県の相沢さんという方が作ったという『かひこ礼讃』が掲載されています。
大変長い和讃ですが、その中に、川尻・蠶養神社周辺の、金色姫譚にまつわるらしい地名が数多く出てきます。
それを、順に並べると、
イワヒ山、コカヒがハマ、蚕島、そだて島、かがて姫島、かくれ磯、ぢい磯、ばあ磯、めをと磯、袖ケ浦、三宝磯、経が島、タテ山、ビヨウブ岩、ボダイ山、マユ磯、蝶島、鍋島、イビラ島、経繰(ヘグリ)の磯、
ザグリ穴、船橋、イト磯、タカラ磯、アヤ磯、錦島、コロモ磯、太夫がヤカタ、外記ヤシキ、赤見台、あまつシミツの井戸、トヨラ潟、えびすの穴、鯛の磯、ベンテン崎、ホテイ岩、ダイコク島、ビシヤモン堂、コカヒがみね
・・・最後のあたりは七福神関係(^^;)ですね
 。
。しかし逆に、金色姫譚と養蚕・織物にまつわる名がつけられた地名、そしてめでたい七福神との混淆が、民衆の生々しい信仰と願いを伝えていると感じます。
現在はそれぞれがどこに該当するのか分からないようですが、少なくともそう呼ばれた地名が当時の頃まではあったということでしょう。
それにしても、この『こかひ礼賛』の名所紹介の箇所を歌うと、この辺りの海岸線や、小島、岩、浜辺の様子が目に浮かぶようです
 。
。(文献7の『筑波歴史散歩』(宮本宣一 著)に、筑波山麓から遠く離れた、貴重な蠶養神社の『かひこ礼讃』が全文記載されている
のは、素晴らしいと思いました。著者は、蚕影山神社の『蚕影山和讃』を元にした例として紹介していますが)
以上述べてきたことを考えると、実はこの日立市川尻地区が、『常陸国における金色姫譚の始まりの地』
の可能性が一番高いのではないかと、私は考えています
 。
。【ジオから見た蠶養神社の信仰】
さてこの地での金色姫伝説については、この土地特有のジオも関わっていると思います。
つまり、この日立市川尻地区の周辺の、海洋生物の生態、地形、地質、海流の条件が見事に重なって、蚕のお守り=サンショウガイや綺麗な小石という民間信仰が生まれた言えるでしょう。
(1) 砂浜の貝殻:鮮やかな赤色の小さな巻貝がある。
昔は浜辺が赤くなるほど、サンショウガイの貝殻があったと云います(文献3、4、6)
その赤い小さな巻貝は『サンショウガイ』
サンショウガイはサザエ科の微小な巻貝。
 参考サイト:微小貝さがしサポートデータベース
参考サイト:微小貝さがしサポートデータベース地元の伝承(文献3、4、6)では『蚕生貝』という字を当てられ、蚕のお守りにするとされたとのこと。
 参考サイト:
参考サイト:日立市HP 金色姫伝説、サンショウガイ
もしかすると、
『赤い』サンショウガイ と 『白い』蚕 ⇒ 赤と白の組み合わせに 『めでたい』 ⇒ 『良い生育』
を、願ったのかもしれませんね
 。
。(2) 砂浜の砂利:きれいな小石。常陸国風土記にも、「碁石」など綺麗な小石の浜があると書かれている。
これも蚕のお守りにするとされたと云います(文献6)。
これは、茨城県北の山で産出する、めのうや玉髄などが川から海に流れていき、きれいな小石の砂利となっているためです。
茨城県北、奥久慈の山はメノウや玉髄の産地です
 。
。 久慈川上流のメノウについては、以前書いた記事もご参照下さい
久慈川上流のメノウについては、以前書いた記事もご参照下さい
→ 茨城こんなもの見つけた♪(23) 常陸大宮の 珪化木 と メノウ
久慈川・十王川水系(久慈川 · 里川 · 茂宮川 · 入四間川 · 落見川、十王川)が、山から風化等で崩れてきたメノウや玉髄を運び、 更にそれらが細かい砂利となって、この辺りの美しい海岸の砂利を作っているのですね。
(3)海流:この土地は外洋に面した土地。

(小貝浜の南に隣接する川尻海水浴場 2020年8月撮影)
そして、この茨城県沖は、黒潮と親潮がぶつかるエリア。
海産物も豊富だが、遠くから流されてくる漂着物も多く、昔から様々なものが流れ着きました。
例えば、文献1では、漂流していた琉球船が流れ着いた記録も記されています。
ご神体とされていた『蚕形』の石(文献11)に書かれた縁起書には、この浦の沖で蚕形のもの(石?)が浮いているのが発見され、それを 上子山(現在の蚕養神社のある高台か?)に安置して、『䗝養濱神虫神石御命』『蚕養大明神 蚕養嶺地主神』『蚕養大明神』としたとあります。
※『䗝』 (『神』の下に『虫』、蚕の異体字)
またその『蚕形』の石が発見された翌日に、『従者のように小石が沢山 流れ着いた』という話も、後から海流に乗って次々に漂着した軽石を思わせます。
海流の関係から、例えば伊豆諸島の火山や海底火山が噴火したら、噴出物の軽石などが流れ着く可能性は大いに考えられます。
(今年2021年の8月小笠原諸島の海底火山「福徳岡ノ場」噴火し、海流に乗った大量のよる軽石が、10月には奄美・沖縄方面に大量に漂着し、11月には千葉県の海岸にも漂着が確認されたニュースの記憶が新しいです)
このようなジオ的な目で見ると、この土地に伝わる信仰についても、また違った風景が見えてきますね。
【おまけ】 つくばにある『蚕養神社』

さて、つくば市上郷、小貝川のほとりにある金村別雷神社。
(写真は金村別雷神社。2021年10月撮影)
その金村別雷神社の境内に、『蚕養神社』があります(※)。
すぐ近く、筑波山麓の蚕影山神社(蚕影神社)でなく、『蚕養神社』なのです!
(※)つくば市内に蚕養神社があるのは、(当時)神栖町歴史民俗資料館が発行した 『第19回企画展 蚕物語 ~天の虫・糸の虫~』(文献 13) の 『茨城県内の養蚕・機織りに関する神社と地名』の地図で見つけ、具体的にどこにあるのか、同資料館に問い合わせたところ、金村別雷神社の境内にあるとご教示頂きました。
神栖市歴史民俗資料館の職員の方、ありがとうございました。

金村別雷神社の本殿の裏手側、複数の祠が並ぶ中に、蚕養神社があります。
(こちらの祠の扁額には『蚕養神社』となってますので、当ブログでもこちらの神社は旧字を使った『蠶養』でなく『蚕養』と書きます)
お詣りされる方が多いのか、小さなお賽銭箱もあり、お酒も奉納されています
 。
。(2021年10月撮影)
上郷地区(旧 豊里町)は、昔は養蚕が盛んな場所でした。
そして先ごろ廃校になってしまいましたが、県立上郷高等学校の前身は、『上郷養蚕高等学校』でした(文献14)。
そういった土地だったので、『蚕養神社』の祠が奉られ、信仰されてきたのでしょう。

しかしなぜ、(筑波山に隣接する)蚕影山に比較的近いこの地に、『蚕影山神社/蚕影神社』ではなくて、『蚕養神社』の祠が建立され、信仰されてきたのでしょうか。
日立・川尻の蚕養神社から分霊したものなのか?はたまた偶然の名前の一致なのか?
神社の方にここの蚕養神社の祠について尋ねましたが、『この辺りにあった小さな祠をまとめたものです』ということで、
詳しいことは分からないとのことでした。
もしご存じの方がおられたら、ご教示下さい。
次回からは、神栖の星福寺/蚕霊神社 について考えていきます。
続きます。
→ 茨城3つの養蚕信仰の聖地について(6)~神栖市 蠶霊神社・星福寺《前編》
************************
【参考文献】
1. 『常陸多賀郡史(復刻版)』 千秋社
2. 『新修 日立市史 上巻』 日立市史編さん委員会 日立市
3. 『ひたち地方の伝説ー郷愁の伝承誌ー』 柴田勇一郎 著 日立市民文化事業団
4. 『日立の伝説』 柴田勇一郎 著 筑波書林 (※ 『ひたち地方の伝説ー郷愁の伝承誌ー』 と同じ内容)
5. 『蚕 絹糸を吐く虫と日本人』 畑中章宏 著 晶文社
6. 『水戸黄門の遊跡 -日立地方の巻-』 鈴木彰 著 崙書房
7. 『筑波歴史散歩』 宮本宣一 著 日経事業出版センター
8. 『茨城県神社誌』 茨城県神社誌編纂委員会 茨城県神社庁
9. 『ヤマトタケルと常陸国風土記』 黒澤彰哉 著 茨城新聞社
10. 『日立市史』 日立市役所 常陸書房
11. 『養蠶の神々-蚕神信仰の民俗-』 阪本英一 著 群馬県文化事業振興会
12. 『地球再発見 いばらき自然ものがたり』 ミュージアムパーク茨城県自然博物館 編 茨城新聞社
いばらきの自然
13. 『第19回企画展 蚕物語 ~天の虫・糸の虫~』 神栖町歴史民俗資料館
14. 『豊里町の歴史』 豊里町史編纂委員会 豊里町
【参考サイト】
微小貝さがしサポートデータベース
http://bishogai-sagashi.jp/search/block.php
http://bishogai-sagashi.jp/sp/
日立市HP 金色姫伝説、サンショウガイ
https://www.city.hitachi.lg.jp/citypromotion/hitachikaze/boasts/view/p092362.html
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム