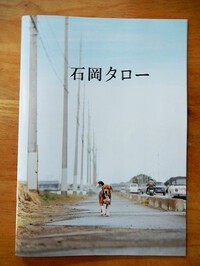2017年04月10日
筑波山神社 春の御座替神事(神幸祭) 2017
筑波山神社 春の御座替神事(神幸祭) 2017
長年行ってみたくて、日程がなかなか合わなくて見ることが出来なかった、
筑波山の春(4/1)/秋(11/1)の御座替祭(おざがわりさい)。
今年2017年の4/1は土曜日だったので、やっと(午後だけですが)行くことが出来ました 。
。
この日は前日から大変寒く、筑波山頂は積雪だったよう(朝はふぶいていたとか・・・) 。
。
昼過ぎに筑波山神社に到着。
この日は、お天気がイマイチのせいもあるのか、それほど人も多くなく。
御座替祭では、小さな御神輿で山を回ってきたあと、
(14:30頃から)6丁目の一の鳥居そばの仮宮で御神体を大きな御神輿に移され(文献1)、その後、大小2つの御神輿は、大人数の行列とともに、
一の鳥居からまっすぐ参詣道(つくば道の終点付近の道)の急な坂を上り、筑波山神社へ戻ります。
筑波山神社ホームページ(http://www.tsukubasanjinja.jp/)によると、
御座替祭は、大きく分けて、『神衣祭(かんみそさい)』、『奉幣祭(ほうべいさい)』、『神幸祭(じんこうさい)』の3つからなるとのことで、今回は、六丁目の一の鳥居から筑波山神社に向かうまでの、神幸祭(じんこうさい)を見学しました。

山頂から小さい御神輿が戻ってきました。
笛の音でお出迎え。
筑波山頂の本殿での衣替えの神事(神衣(かんみそ)祭)で、秋の御座替祭の時から冬の間中、山頂の本殿にあった神衣(※)が運ばれて戻ってきます。
※神様の衣『かんみそ』の漢字表記は、文献によっては『神衣』だったり『神御衣』だったりしますが、ここでは筑波山神社ホームページの表記『神衣』にします。
なお半年間、山頂の本殿にあた神衣は、細片にして御守として領布されるとのこと(文献1)。

6丁目の一の鳥居のそばの御仮屋/御假屋(おかりや)にて。
(御仮屋/御假屋の名称は文献2/文献3より)
①白い布で覆いがされて、神官の方が何やら中で神事をされている模様。
多分、小さな御神輿から大きな御神輿へと、御神体(この場合は神衣でしょうか)を移しているのかと推察。

御仮屋/御假屋にて。
山を巡ってきた小神輿と、これから神社に戻る大神輿が並んだところ。
②氏子代表や各団体代表がお祓いを受け、神官による神事の後、
(①の神事もしくは②の神事(または①②両方か)を、文献1では『出立祭』、文献2では『“境迎え(さかむかえ)”の神事』と呼んでいます)

サルタヒコ神に扮した方を先頭に、大小の御神輿や弓矢・鉾等の神宝類とともに、行列一行は参道を登ります。

きつい坂を登るので(特に御神輿は大変)、途中、何箇所か御神輿お休み処があり、一行は休み休み上がっていきます。
遠くに、山麓の平野部が見えます。
勾配のキツさが分かるかと。

さて、御神輿が通る参詣道では、参道のお宅に、紙垂(しで)と麻糸が結ばれた榊の枝(玉串というのでしょうか)を配っておられました。
まさに『神幸』祭ですね。
そしてなんと!沿道にいる参詣者・見学者にも、同じように榊の枝が♪
私も頂きました。すごくうれしい(*^^*)

こちらは大きい御神輿が、参道にある、旧筑波郵便局前を通っているところ。
旧筑波郵便局 については、以前2度ほど書いたので良かったら。
 → 【つくばのレトロ建築めぐり6】 旧筑波山郵便局
→ 【つくばのレトロ建築めぐり6】 旧筑波山郵便局
 → 茨城こんなもの見つけた♪(30) 旧筑波郵便局の記念切手
→ 茨城こんなもの見つけた♪(30) 旧筑波郵便局の記念切手

大きい御神輿の後ろを、白い衣装を着た若い担ぎ手の皆さんが、小さい御神輿を担いでいきます。
私たちは、ここで時間切れとなり帰宅しましたが、御神輿が戻った筑波山神社ではまた神事(還御祭)があるそうです(文献1)。

年に3回だけ渡れる、筑波山神社のご神橋。
春の御座替祭のこの日も渡れる日でした。一般の人も渡れます。

いつもと違う景色に、ちょっと興奮♪
ご神橋から、鳥居を見たところ。
手前につくば観光ボランティアの皆さんの待機ウッドハウスがあり、ボランティアの方が案内中。
この橋を渡る御神輿が見られなかったのはちょっと残念。
またの機会を楽しみにします。
【おまけ】

大御堂で、新しい参道の階段が整備されつつありました。
近くのお土産屋さんの方に伺ったら、建物も新しくなるそうです。
こちらも楽しみですね(^^)
-----------------------------------------------------------------------------------
【参考文献】
1.『古代筑波の謎』 矢作幸雄 著 学生社
2.『茨城の神事』 茨城県神社庁
3.『郷土の達人とゆく筑波山』 結エディット
【参考ホームページ】
1.筑波山神社 公式ホームページ http://www.tsukubasanjinja.jp/
長年行ってみたくて、日程がなかなか合わなくて見ることが出来なかった、
筑波山の春(4/1)/秋(11/1)の御座替祭(おざがわりさい)。
今年2017年の4/1は土曜日だったので、やっと(午後だけですが)行くことが出来ました
 。
。この日は前日から大変寒く、筑波山頂は積雪だったよう(朝はふぶいていたとか・・・)
 。
。昼過ぎに筑波山神社に到着。
この日は、お天気がイマイチのせいもあるのか、それほど人も多くなく。
御座替祭では、小さな御神輿で山を回ってきたあと、
(14:30頃から)6丁目の一の鳥居そばの仮宮で御神体を大きな御神輿に移され(文献1)、その後、大小2つの御神輿は、大人数の行列とともに、
一の鳥居からまっすぐ参詣道(つくば道の終点付近の道)の急な坂を上り、筑波山神社へ戻ります。
筑波山神社ホームページ(http://www.tsukubasanjinja.jp/)によると、
御座替祭は、大きく分けて、『神衣祭(かんみそさい)』、『奉幣祭(ほうべいさい)』、『神幸祭(じんこうさい)』の3つからなるとのことで、今回は、六丁目の一の鳥居から筑波山神社に向かうまでの、神幸祭(じんこうさい)を見学しました。

山頂から小さい御神輿が戻ってきました。
笛の音でお出迎え。
筑波山頂の本殿での衣替えの神事(神衣(かんみそ)祭)で、秋の御座替祭の時から冬の間中、山頂の本殿にあった神衣(※)が運ばれて戻ってきます。
※神様の衣『かんみそ』の漢字表記は、文献によっては『神衣』だったり『神御衣』だったりしますが、ここでは筑波山神社ホームページの表記『神衣』にします。
なお半年間、山頂の本殿にあた神衣は、細片にして御守として領布されるとのこと(文献1)。

6丁目の一の鳥居のそばの御仮屋/御假屋(おかりや)にて。
(御仮屋/御假屋の名称は文献2/文献3より)
①白い布で覆いがされて、神官の方が何やら中で神事をされている模様。
多分、小さな御神輿から大きな御神輿へと、御神体(この場合は神衣でしょうか)を移しているのかと推察。

御仮屋/御假屋にて。
山を巡ってきた小神輿と、これから神社に戻る大神輿が並んだところ。
②氏子代表や各団体代表がお祓いを受け、神官による神事の後、
(①の神事もしくは②の神事(または①②両方か)を、文献1では『出立祭』、文献2では『“境迎え(さかむかえ)”の神事』と呼んでいます)

サルタヒコ神に扮した方を先頭に、大小の御神輿や弓矢・鉾等の神宝類とともに、行列一行は参道を登ります。

きつい坂を登るので(特に御神輿は大変)、途中、何箇所か御神輿お休み処があり、一行は休み休み上がっていきます。
遠くに、山麓の平野部が見えます。
勾配のキツさが分かるかと。

さて、御神輿が通る参詣道では、参道のお宅に、紙垂(しで)と麻糸が結ばれた榊の枝(玉串というのでしょうか)を配っておられました。
まさに『神幸』祭ですね。
そしてなんと!沿道にいる参詣者・見学者にも、同じように榊の枝が♪
私も頂きました。すごくうれしい(*^^*)

こちらは大きい御神輿が、参道にある、旧筑波郵便局前を通っているところ。
旧筑波郵便局 については、以前2度ほど書いたので良かったら。
 → 【つくばのレトロ建築めぐり6】 旧筑波山郵便局
→ 【つくばのレトロ建築めぐり6】 旧筑波山郵便局 → 茨城こんなもの見つけた♪(30) 旧筑波郵便局の記念切手
→ 茨城こんなもの見つけた♪(30) 旧筑波郵便局の記念切手大きい御神輿の後ろを、白い衣装を着た若い担ぎ手の皆さんが、小さい御神輿を担いでいきます。
私たちは、ここで時間切れとなり帰宅しましたが、御神輿が戻った筑波山神社ではまた神事(還御祭)があるそうです(文献1)。

年に3回だけ渡れる、筑波山神社のご神橋。
春の御座替祭のこの日も渡れる日でした。一般の人も渡れます。

いつもと違う景色に、ちょっと興奮♪
ご神橋から、鳥居を見たところ。
手前につくば観光ボランティアの皆さんの待機ウッドハウスがあり、ボランティアの方が案内中。
この橋を渡る御神輿が見られなかったのはちょっと残念。
またの機会を楽しみにします。
【おまけ】

大御堂で、新しい参道の階段が整備されつつありました。
近くのお土産屋さんの方に伺ったら、建物も新しくなるそうです。
こちらも楽しみですね(^^)
-----------------------------------------------------------------------------------
【参考文献】
1.『古代筑波の謎』 矢作幸雄 著 学生社
2.『茨城の神事』 茨城県神社庁
3.『郷土の達人とゆく筑波山』 結エディット
【参考ホームページ】
1.筑波山神社 公式ホームページ http://www.tsukubasanjinja.jp/
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (三)
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (二)
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (一)
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(9) 地元の方から教えて頂いた神栖に伝わるお話
国立歴史民俗博物館 企画展 『陰陽師とは何者か』 を見て
映画『石岡タロー』
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (二)
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (一)
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(9) 地元の方から教えて頂いた神栖に伝わるお話
国立歴史民俗博物館 企画展 『陰陽師とは何者か』 を見て
映画『石岡タロー』
Posted by かるだ もん at 22:57│Comments(0)│茨城&つくば プチ民俗学・歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム