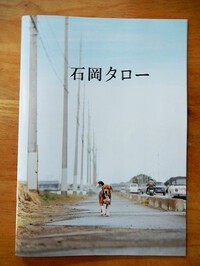2012年05月02日
だいだらぼっちの足跡を探して(3) 利根町、結城市、八千代町
【つくば・茨城プチ民俗学】 だいだらぼっちの足跡を探して(3) 利根町、結城市、八千代町
(初出: 2012年5月02日 22時06分)
※2012年4月15日放送 ラヂオつくば「つくば井戸端レポーター」の放送内容を再構築しています。
自称つくば近郊ローカルミステリーハンター かるだもんが、茨城県南、県西で、巨人伝説「だいだらぼっち(だいだらぼう)」伝説の伝わる土地を訪ねるシリーズ第3弾。
今までのお話は
だいだらぼっちの足跡を探して(1) つくば市、桜川市(旧真壁町、旧大和村)
だいだらぼっちの足跡を探して(2) 桜川市(旧岩瀬町)、石岡市、守谷市
利根町、結城市、八千代町でも見つけました!
まずは、クイズ。 お分かりになりますか。
--------------------------------------------------
【Q1】(利根町の伝説より)昔、現在千葉県の、印旛沼・手賀沼付近にあって、だいだらぼっちによって移動させられたものは何でしょうか?
【Q2】(結城に伝わるダイダラボウ伝説より)だいだらぼっちが運ぼうとしたのは、筑波山と何でしょうか? 結城市から見える景色ならでは です。
【Q3】八千代町のダイダラボウ沼の主は「片目のどじょう」です。ところで、日本各地では「片目の魚」の伝説が多く伝わっていますが、一説によると「片目の魚」は何の象徴と言われているでしょう。
---------------------------------------------------
答えは本文をどうぞ!
1.(北相馬郡)利根町
茨城県の一番南の端に位置し、利根川をはさんで千葉県と隣り合っている利根町。
町の西にある小貝川の下流域 及び、利根川との合流域は、江戸時代初頭に幕府の利根川東遷事業により、台地を削って造られた人口の川です。
従って、度重なる水害に襲われながらも、水運の町として栄えてきた場所でもあります。
現在は、見渡す限りの肥沃な水田・畑作地帯が続く農業地帯です。
さて、利根町には2つ、パターンの違う ダイダラボッチ伝説が伝わっているようです。
・ あの山が、昔はあんな所に!?
利根町付近の伝説のよると、昔、筑波山は利根町の南側の千葉県側にあったそうです。
そのため、利根町のあたりは日当りが悪くて農作物が育たず、困っていたそうです。その嘆きを知ったダイダラボウが、「それなら俺が筑波山をちょっくら動かしてやっぺ」と、筑波山を今の場所に運んだそうです。(文献1)

手賀沼(千葉県)
その時、土を掘りすぎて、その後が印旛沼や手賀沼なり、踏ん張った足跡が牛久沼や霞ケ浦になったそうです。
・・・地図を見ると、この伝説では、筑波山は、今の印西市、我孫子市、成田市あたりにあったようですね 。
。
というわけで、第一問目のクイズの答えは、筑波山でした。

←写真は、「大房」バス停
ちなみのこのお話が伝わる大房地区の「だいぼう」は、「だいだらぼう」が住んでいたからと伝わっているそうです。
・ 脱いだ笠が重くて・・・
さて、もう一つ、利根町に伝わるダイダラボウ伝説があります。
 広大な田畑の中にポツンと池が。
広大な田畑の中にポツンと池が。
上述の大房地区にも近い、利根町立木地区には、今でも笠脱沼(かさぬきぬま)という、小さな沼というか池が、見渡す限りの水田の中にポツンとあります。
立木地区に伝わる伝説によると、
昔、ダイダラの神様がこの地においでになり、笠を脱いで休憩したそうです。そうしたら笠の重みで窪みができて、そこに水がたまって沼になったそうです。
そこで土地の人々はその池を「笠脱沼(笠貫沼とも)」と呼ぶようになったそうです。
また、その時ダイダラの神は着ていた蓑も脱いで近くの榎(えのき)の木にかけたそうで、その木は「蓑かけ榎」と呼ばれたそうです(文献2)。
 すぐ近くにある蛟蝄神社の看板
すぐ近くにある蛟蝄神社の看板
さて、この笠脱沼は、この近くにある「蛟蝄(こうもう)神社」の神池(かみいけ)とのことです(文献3)。
この蛟蝄神社は大変古い神社で、祭神は水の神様である「罔象女大神(みつはのめのおおかみ)」を祀っています。神社の名前にある「蛟」は「みつち=伝説上の龍」とのことで、やはり雨や水にかかわりの深い名前です。
そういう神社の神池が笠脱沼ということで、雨乞い神事と関係があるのではないかなと思っています。
 笠脱沼からやじり塚を望む。
笠脱沼からやじり塚を望む。
向こう側のこんもり樹が茂っているのがやじり塚。
さて、笠脱沼の近くに、古い樹が数本立っている塚があって、最初これが「蓑かけ榎」かと思っていたのですが、地元の利根町のことを詳しく調べて発信されている、タヌポンさんのHPによると、これは全く別の伝説が伝わる「やじり塚」とのことです。
また、「蓑かけ榎」についても、タヌポンさんから教えて頂いたのですが、落雷で焼失してしまったそうです。
蛟蝄神社の宮司さんのお話とのことで、落雷とはいえ、残念です。(ありし日の「蓑かけ榎」の写真は文献2に載っています)
※タヌポンさんのHP「タヌポンの利根ぽんぽ行」: http://toneponpokou.tanuki-bayashi.com/
2.結城市
・土地を広げたくて運ぼうととしたもの
さて次は、県の西端、鬼怒川をはさんで栃木県と接する結城市に行きます。
結城は言うまでもなく、歴史の町、そして結城紬の町です。
ということで、二問目の問題は、結城に伝わるダイダラボウ伝説からです(文献4)。
だいだらぼっちが重さを比べようとしたのは、筑波山と何でしょうか? 結城市から見える景色ならではです。
結城に伝わる伝説は、今まで見てきたダイダラボッチ伝説のパターンをほぼ全部取り揃えているといっても良い、豪華な(?)伝説で、
あらすじは、
「村の人が狭い土地を耕しているのを見て、もっと広い土地をあげたいと思った大男のダイダラボウが、筑波山と太平山(おおひらさん・栃木県)を綱でつるして天秤棒で運ぼうとしました。
ところが棒がはねてしまい、太平山が二つに割れてしまい、その割れた一つが太平山の北に落ちて錦着山(きんちゃくさん)になった。運ぶことに失敗してがっかりしたダイダラボウは、思わず筑波山の山頂に座ってしまい、筑波山のてっぺんが凹んでしまった。
また踏ん張った時に出来た水たまりが、旧結城町南東の田んぼに出来て「ダイダラボウの足跡」と呼ばれた。その足跡の沼も農地改良のために今では見られなくなった」
というお話です。
…ということで、第二問の答え、結城に伝わる伝説では、ダイダラボウが運ぼうとしたのは、筑波山ともうひとつ、太平山でした。
今の私たちの感覚では、広い関東平野に位置する結城市は、十分に広い土地を持っていると思えます。
しかし、河川に囲まれ、昔は水害に悩まされ続けた土地でもあり、「安心して耕せる土地」は人々の切実なる願いだったことでしょう。そこから、筑波山・太平山を運ぼうとするだいだらぼっち・・・というモチーフが生まれたのかと想像します。
 結城から太平山方面を望む
結城から太平山方面を望む
さて、太平山は343mの山で、結城からみても、筑波山よりはるかに小さな山です。しかも日光連山の西側の端のあたりに見え、目立つ山と言えば、大平山より日光の男体山などの方が目立ちます。
にも関わらず、太平山が選ばれた所に、何か話が語り継がれていくための隠されたバックグランドのようなものがあるように感じます。
 上記と同じ場所から筑波山を望む
上記と同じ場所から筑波山を望む
ちなみに、以前もこの番組で紹介しましたが、筑波山から冬至の日の出が見えるラインのすぐ近くに太平山はあり、実際お正月の頃、筑波山山頂ではありませんが筑波山付近からのご来朝が見られるようです。
また、幕末の水戸天狗党も、筑波山で決起した後、太平山に移動してそこに籠ってます。
何か意識の中でつなぐものがあるのかなと興味深く思います。
 「健田神社跡と遠くに見える筑波山」
「健田神社跡と遠くに見える筑波山」
旧結城町にあった、「だいだらぼうの足跡」と呼ばれた水たまり(沼?)は、現在、結城のどこあたりにあったのか不明なのですが、「旧結城町の南東」という言葉を頼りに、そのあたりに該当しそうな水田地帯に行ってみました。
すると、塚があり「健田(たけだ)神社跡」という史跡がありました(「結城百選 延喜式内健田神社跡地と結城筑波」という碑もあり)。
 健田神社跡付近から太平山方面を望む。建物で見えにくいです。
健田神社跡付近から太平山方面を望む。建物で見えにくいです。
そこの石碑によると、創建が非常に古く、927年の延喜式の記録には載っていて、祭神は結城国造の竹田一族の始祖タケヌナカワワケノミコトだったそうです。
この土地を古く開拓した一族の始祖が祀られていう神社跡なので、もしかするとこの辺りにダイダラボウの足跡があっても良さそうに思うんですが、地元でご存じの方がいらっしゃりましたら教えて頂けると幸いです。
(健田神社は、現在、健田須賀神社(たけだすが神社)に合祀されているとのことです)
3.結城郡八千代町
・「片目の魚」は何を表す?
さて最後は結城市の南に隣接する、結城郡八千代町に伝わるダイダラボウ伝説です。
ここでの伝説は、直接ダイダラボウは出てこないで、「ダイダラボウ」という呼ばれる沼に住む「片目のドジョウ」と雨乞いにまつわるお話です(文献5)。
 「昔、瀬戸井村という村に、ダイダラボウと呼ばれる沼がありました。
「昔、瀬戸井村という村に、ダイダラボウと呼ばれる沼がありました。
その昔、村人のヤスで片目を突かれたドジョウが巨大になって住んでいる沼で、村人が近づかなくなっていましたが、日照り続きのある夏、祈祷の為ににダイダラボウの池の水が必要になったにも関わらず、池も干上がって水はありません。
「ダイダラボウの沼は片目のドジョウがいるから水は干上がらない」という伝説を信じたある村人が、池の底の地面を掘ると水が湧き出した。
無事祈祷用の水が確保できて雨乞えの祈祷をしたところ、雨が降って日照りが解消され、水をたたえた沼にはまた片目のドジョウが出て泳いでいました」
というストーリー。
 「だいだらぼう」沼の跡地と思われる水田。
「だいだらぼう」沼の跡地と思われる水田。
この沼があった所も、今では水田地帯となってしまったそうですが、明治時代の地図(※)を見ると、「瀬戸井村」のエリアに「水」と書かれた沼か池のような丸い場所があります。
たぶんこれが「ダイダラボウ」沼でないかと判断し、行ってみました。するとそこだけ区画的に丸い形で周りの田畑よりちょっと低めの田んぼがありました。
※(独)農業環境技術研究所 「歴史的農業環境閲覧システム」 http://habs.dc.affrc.go.jp/
 付近から見た筑波山
付近から見た筑波山
ちょうど訪ねた時、田植えの準備にトラクターが苗代作りを始めつつある時でした。
さてここで最後の問題、 八千代町のダイダラボウ沼の主は「片目のどじょう」のように、日本各地では「片目の魚」の伝説が多く伝わっています。一説によると「片目の魚」は何の象徴と言われているでしょう。
これは、日本民俗学の父と呼ばれる柳田國男の説(文献6)ですが、「いけにえ」の象徴という説があります。大昔、いけにえとして神に捧げる人間が逃亡しないように、片目にしたり、片足にしたりしたことに端を発し、神に捧げる生き物のしるしとして、片目を潰したその名残…という説です。
とうことで、答えは、「片目の魚」は「神に捧げるいけにえの象徴」です。
ダイダラボウ伝説は、国造り・土地作りの神様的伝説の他に、利根町の笠脱池、八千代町のダイダラボウの沼のように、雨乞いの神事との関係も見られる のが大変興味深いです。
以上、今回は県南の利根町、県西に結城市、八千代町に伝わる、ダイダラボウ・ダイダラボッチ伝説を訪ねてみました。
今回訪ねた場所の地図 → http://g.co/maps/69cra
------------------------------------------------------------------------------
参考文献
1.「利根町史 第4巻 民俗編」 利根町教育委員会
2.「利根町の昔ばなし」 高橋馨 著 崙書房
3.「角川日本地名大辞典 8 茨城県」 角川書店
4.「結城昔ばなし」 なかむら さぶろう 著/植野昭 画
5.「八千代町の伝説と昔話 上」 八千代町教育委員会
6.「柳田國男全集6 ちくま文庫」 柳田國男 著 筑摩書房
参考WEBサイト
「タヌポンの利根ぽんぽ行」: http://toneponpokou.tanuki-bayashi.com/
(独)農業環境技術研究所 「歴史的農業環境閲覧システム」 http://habs.dc.affrc.go.jp/
掲載当時に頂いた コメント
力作レポート、お疲れ様です。また、拙サイトをご紹介いただきありがとうございます。
現地各所を実際に訪問され、時間をかけて取材されたのがよく分かります。
だいだらぼうのお話もさることながら、「片目の・・・」の真相には、なるほどと思いました。でも、ちょっとかわいそうな感じもしますね。
これからも益々のご活躍をお祈り申し上げます。
PS わたしのサイトでも、かるだもんさんのこのレポートをいつか「参考文献」としてご紹介できればと思っています。その節は、ご連絡いたします。よろしくお願いします。
by tanupon URL at 5月3日 14時45分
tanupon様
ラジオお聞きの上、お読み頂きありがとうございます!
調べれば調べるほど、いろいろなことがわかったり、逆に謎が深まったり、興味が膨らんでいきます。
笠脱沼は冬枯れの田の中で、満々と水をたたえているのが大変不思議な光景でした。周りから水が流入しているというより、水が湧いているようにも見えたのですが、どうなのでしょうか。
利根町に行った時は大荒れの天気の日で、蛟蝄神社に行けなかったのが残念だったので、今度行ってみたいです。
専門家でないので、トンデモなことも多々書いていると承知していますが、ぼちぼちと、資料やお話で知識が増え次第、直していけたら・・・と思っています。
こちらこそ、今後ともご教示よろしくお願い申し上げます。
by かるだもん at 5月4日 10時20分
(初出: 2012年5月02日 22時06分)
※2012年4月15日放送 ラヂオつくば「つくば井戸端レポーター」の放送内容を再構築しています。
自称つくば近郊ローカルミステリーハンター かるだもんが、茨城県南、県西で、巨人伝説「だいだらぼっち(だいだらぼう)」伝説の伝わる土地を訪ねるシリーズ第3弾。
今までのお話は
だいだらぼっちの足跡を探して(1) つくば市、桜川市(旧真壁町、旧大和村)
だいだらぼっちの足跡を探して(2) 桜川市(旧岩瀬町)、石岡市、守谷市
利根町、結城市、八千代町でも見つけました!
まずは、クイズ。 お分かりになりますか。
--------------------------------------------------
【Q1】(利根町の伝説より)昔、現在千葉県の、印旛沼・手賀沼付近にあって、だいだらぼっちによって移動させられたものは何でしょうか?
【Q2】(結城に伝わるダイダラボウ伝説より)だいだらぼっちが運ぼうとしたのは、筑波山と何でしょうか? 結城市から見える景色ならでは です。
【Q3】八千代町のダイダラボウ沼の主は「片目のどじょう」です。ところで、日本各地では「片目の魚」の伝説が多く伝わっていますが、一説によると「片目の魚」は何の象徴と言われているでしょう。
---------------------------------------------------
答えは本文をどうぞ!
1.(北相馬郡)利根町
茨城県の一番南の端に位置し、利根川をはさんで千葉県と隣り合っている利根町。
町の西にある小貝川の下流域 及び、利根川との合流域は、江戸時代初頭に幕府の利根川東遷事業により、台地を削って造られた人口の川です。
従って、度重なる水害に襲われながらも、水運の町として栄えてきた場所でもあります。
現在は、見渡す限りの肥沃な水田・畑作地帯が続く農業地帯です。
さて、利根町には2つ、パターンの違う ダイダラボッチ伝説が伝わっているようです。
・ あの山が、昔はあんな所に!?
利根町付近の伝説のよると、昔、筑波山は利根町の南側の千葉県側にあったそうです。
そのため、利根町のあたりは日当りが悪くて農作物が育たず、困っていたそうです。その嘆きを知ったダイダラボウが、「それなら俺が筑波山をちょっくら動かしてやっぺ」と、筑波山を今の場所に運んだそうです。(文献1)

手賀沼(千葉県)
その時、土を掘りすぎて、その後が印旛沼や手賀沼なり、踏ん張った足跡が牛久沼や霞ケ浦になったそうです。
・・・地図を見ると、この伝説では、筑波山は、今の印西市、我孫子市、成田市あたりにあったようですね
 。
。というわけで、第一問目のクイズの答えは、筑波山でした。
←写真は、「大房」バス停
ちなみのこのお話が伝わる大房地区の「だいぼう」は、「だいだらぼう」が住んでいたからと伝わっているそうです。
・ 脱いだ笠が重くて・・・
さて、もう一つ、利根町に伝わるダイダラボウ伝説があります。
 広大な田畑の中にポツンと池が。
広大な田畑の中にポツンと池が。上述の大房地区にも近い、利根町立木地区には、今でも笠脱沼(かさぬきぬま)という、小さな沼というか池が、見渡す限りの水田の中にポツンとあります。
立木地区に伝わる伝説によると、
昔、ダイダラの神様がこの地においでになり、笠を脱いで休憩したそうです。そうしたら笠の重みで窪みができて、そこに水がたまって沼になったそうです。
そこで土地の人々はその池を「笠脱沼(笠貫沼とも)」と呼ぶようになったそうです。
また、その時ダイダラの神は着ていた蓑も脱いで近くの榎(えのき)の木にかけたそうで、その木は「蓑かけ榎」と呼ばれたそうです(文献2)。
さて、この笠脱沼は、この近くにある「蛟蝄(こうもう)神社」の神池(かみいけ)とのことです(文献3)。
この蛟蝄神社は大変古い神社で、祭神は水の神様である「罔象女大神(みつはのめのおおかみ)」を祀っています。神社の名前にある「蛟」は「みつち=伝説上の龍」とのことで、やはり雨や水にかかわりの深い名前です。
そういう神社の神池が笠脱沼ということで、雨乞い神事と関係があるのではないかなと思っています。
 笠脱沼からやじり塚を望む。
笠脱沼からやじり塚を望む。向こう側のこんもり樹が茂っているのがやじり塚。
さて、笠脱沼の近くに、古い樹が数本立っている塚があって、最初これが「蓑かけ榎」かと思っていたのですが、地元の利根町のことを詳しく調べて発信されている、タヌポンさんのHPによると、これは全く別の伝説が伝わる「やじり塚」とのことです。
また、「蓑かけ榎」についても、タヌポンさんから教えて頂いたのですが、落雷で焼失してしまったそうです。
蛟蝄神社の宮司さんのお話とのことで、落雷とはいえ、残念です。(ありし日の「蓑かけ榎」の写真は文献2に載っています)
※タヌポンさんのHP「タヌポンの利根ぽんぽ行」: http://toneponpokou.tanuki-bayashi.com/
2.結城市
・土地を広げたくて運ぼうととしたもの
さて次は、県の西端、鬼怒川をはさんで栃木県と接する結城市に行きます。
結城は言うまでもなく、歴史の町、そして結城紬の町です。
ということで、二問目の問題は、結城に伝わるダイダラボウ伝説からです(文献4)。
だいだらぼっちが重さを比べようとしたのは、筑波山と何でしょうか? 結城市から見える景色ならではです。
結城に伝わる伝説は、今まで見てきたダイダラボッチ伝説のパターンをほぼ全部取り揃えているといっても良い、豪華な(?)伝説で、
あらすじは、
「村の人が狭い土地を耕しているのを見て、もっと広い土地をあげたいと思った大男のダイダラボウが、筑波山と太平山(おおひらさん・栃木県)を綱でつるして天秤棒で運ぼうとしました。
ところが棒がはねてしまい、太平山が二つに割れてしまい、その割れた一つが太平山の北に落ちて錦着山(きんちゃくさん)になった。運ぶことに失敗してがっかりしたダイダラボウは、思わず筑波山の山頂に座ってしまい、筑波山のてっぺんが凹んでしまった。
また踏ん張った時に出来た水たまりが、旧結城町南東の田んぼに出来て「ダイダラボウの足跡」と呼ばれた。その足跡の沼も農地改良のために今では見られなくなった」
というお話です。
…ということで、第二問の答え、結城に伝わる伝説では、ダイダラボウが運ぼうとしたのは、筑波山ともうひとつ、太平山でした。
今の私たちの感覚では、広い関東平野に位置する結城市は、十分に広い土地を持っていると思えます。
しかし、河川に囲まれ、昔は水害に悩まされ続けた土地でもあり、「安心して耕せる土地」は人々の切実なる願いだったことでしょう。そこから、筑波山・太平山を運ぼうとするだいだらぼっち・・・というモチーフが生まれたのかと想像します。
 結城から太平山方面を望む
結城から太平山方面を望むさて、太平山は343mの山で、結城からみても、筑波山よりはるかに小さな山です。しかも日光連山の西側の端のあたりに見え、目立つ山と言えば、大平山より日光の男体山などの方が目立ちます。
にも関わらず、太平山が選ばれた所に、何か話が語り継がれていくための隠されたバックグランドのようなものがあるように感じます。
 上記と同じ場所から筑波山を望む
上記と同じ場所から筑波山を望むちなみに、以前もこの番組で紹介しましたが、筑波山から冬至の日の出が見えるラインのすぐ近くに太平山はあり、実際お正月の頃、筑波山山頂ではありませんが筑波山付近からのご来朝が見られるようです。
また、幕末の水戸天狗党も、筑波山で決起した後、太平山に移動してそこに籠ってます。
何か意識の中でつなぐものがあるのかなと興味深く思います。
 「健田神社跡と遠くに見える筑波山」
「健田神社跡と遠くに見える筑波山」旧結城町にあった、「だいだらぼうの足跡」と呼ばれた水たまり(沼?)は、現在、結城のどこあたりにあったのか不明なのですが、「旧結城町の南東」という言葉を頼りに、そのあたりに該当しそうな水田地帯に行ってみました。
すると、塚があり「健田(たけだ)神社跡」という史跡がありました(「結城百選 延喜式内健田神社跡地と結城筑波」という碑もあり)。
 健田神社跡付近から太平山方面を望む。建物で見えにくいです。
健田神社跡付近から太平山方面を望む。建物で見えにくいです。そこの石碑によると、創建が非常に古く、927年の延喜式の記録には載っていて、祭神は結城国造の竹田一族の始祖タケヌナカワワケノミコトだったそうです。
この土地を古く開拓した一族の始祖が祀られていう神社跡なので、もしかするとこの辺りにダイダラボウの足跡があっても良さそうに思うんですが、地元でご存じの方がいらっしゃりましたら教えて頂けると幸いです。
(健田神社は、現在、健田須賀神社(たけだすが神社)に合祀されているとのことです)
3.結城郡八千代町
・「片目の魚」は何を表す?
さて最後は結城市の南に隣接する、結城郡八千代町に伝わるダイダラボウ伝説です。
ここでの伝説は、直接ダイダラボウは出てこないで、「ダイダラボウ」という呼ばれる沼に住む「片目のドジョウ」と雨乞いにまつわるお話です(文献5)。
その昔、村人のヤスで片目を突かれたドジョウが巨大になって住んでいる沼で、村人が近づかなくなっていましたが、日照り続きのある夏、祈祷の為ににダイダラボウの池の水が必要になったにも関わらず、池も干上がって水はありません。
「ダイダラボウの沼は片目のドジョウがいるから水は干上がらない」という伝説を信じたある村人が、池の底の地面を掘ると水が湧き出した。
無事祈祷用の水が確保できて雨乞えの祈祷をしたところ、雨が降って日照りが解消され、水をたたえた沼にはまた片目のドジョウが出て泳いでいました」
というストーリー。
 「だいだらぼう」沼の跡地と思われる水田。
「だいだらぼう」沼の跡地と思われる水田。この沼があった所も、今では水田地帯となってしまったそうですが、明治時代の地図(※)を見ると、「瀬戸井村」のエリアに「水」と書かれた沼か池のような丸い場所があります。
たぶんこれが「ダイダラボウ」沼でないかと判断し、行ってみました。するとそこだけ区画的に丸い形で周りの田畑よりちょっと低めの田んぼがありました。
※(独)農業環境技術研究所 「歴史的農業環境閲覧システム」 http://habs.dc.affrc.go.jp/
 付近から見た筑波山
付近から見た筑波山ちょうど訪ねた時、田植えの準備にトラクターが苗代作りを始めつつある時でした。
さてここで最後の問題、 八千代町のダイダラボウ沼の主は「片目のどじょう」のように、日本各地では「片目の魚」の伝説が多く伝わっています。一説によると「片目の魚」は何の象徴と言われているでしょう。
これは、日本民俗学の父と呼ばれる柳田國男の説(文献6)ですが、「いけにえ」の象徴という説があります。大昔、いけにえとして神に捧げる人間が逃亡しないように、片目にしたり、片足にしたりしたことに端を発し、神に捧げる生き物のしるしとして、片目を潰したその名残…という説です。
とうことで、答えは、「片目の魚」は「神に捧げるいけにえの象徴」です。
ダイダラボウ伝説は、国造り・土地作りの神様的伝説の他に、利根町の笠脱池、八千代町のダイダラボウの沼のように、雨乞いの神事との関係も見られる のが大変興味深いです。
以上、今回は県南の利根町、県西に結城市、八千代町に伝わる、ダイダラボウ・ダイダラボッチ伝説を訪ねてみました。
今回訪ねた場所の地図 → http://g.co/maps/69cra
------------------------------------------------------------------------------
参考文献
1.「利根町史 第4巻 民俗編」 利根町教育委員会
2.「利根町の昔ばなし」 高橋馨 著 崙書房
3.「角川日本地名大辞典 8 茨城県」 角川書店
4.「結城昔ばなし」 なかむら さぶろう 著/植野昭 画
5.「八千代町の伝説と昔話 上」 八千代町教育委員会
6.「柳田國男全集6 ちくま文庫」 柳田國男 著 筑摩書房
参考WEBサイト
「タヌポンの利根ぽんぽ行」: http://toneponpokou.tanuki-bayashi.com/
(独)農業環境技術研究所 「歴史的農業環境閲覧システム」 http://habs.dc.affrc.go.jp/
掲載当時に頂いた コメント
力作レポート、お疲れ様です。また、拙サイトをご紹介いただきありがとうございます。
現地各所を実際に訪問され、時間をかけて取材されたのがよく分かります。
だいだらぼうのお話もさることながら、「片目の・・・」の真相には、なるほどと思いました。でも、ちょっとかわいそうな感じもしますね。
これからも益々のご活躍をお祈り申し上げます。
PS わたしのサイトでも、かるだもんさんのこのレポートをいつか「参考文献」としてご紹介できればと思っています。その節は、ご連絡いたします。よろしくお願いします。
by tanupon URL at 5月3日 14時45分
tanupon様
ラジオお聞きの上、お読み頂きありがとうございます!
調べれば調べるほど、いろいろなことがわかったり、逆に謎が深まったり、興味が膨らんでいきます。
笠脱沼は冬枯れの田の中で、満々と水をたたえているのが大変不思議な光景でした。周りから水が流入しているというより、水が湧いているようにも見えたのですが、どうなのでしょうか。
利根町に行った時は大荒れの天気の日で、蛟蝄神社に行けなかったのが残念だったので、今度行ってみたいです。
専門家でないので、トンデモなことも多々書いていると承知していますが、ぼちぼちと、資料やお話で知識が増え次第、直していけたら・・・と思っています。
こちらこそ、今後ともご教示よろしくお願い申し上げます。
by かるだもん at 5月4日 10時20分
この記事へのコメント
でいだらぼっちや、ひたち帯、神社など、調べているとカルダモンさんに繋がることが多く、お気に入りに入れさせていただいて時折読ませていただいています。ありがとうございます
巨人伝説は世界中にありますね(70年代に翻訳された南米の古い昔話を読んだことがあります)。どれも心優しい話が共通しているように思われます。わたし、彼らを知っている❗と不思議な感覚があり、その感覚を思い出したくて読んでしまいます(笑)余談でした。いつもありがとうございます❗
巨人伝説は世界中にありますね(70年代に翻訳された南米の古い昔話を読んだことがあります)。どれも心優しい話が共通しているように思われます。わたし、彼らを知っている❗と不思議な感覚があり、その感覚を思い出したくて読んでしまいます(笑)余談でした。いつもありがとうございます❗
Posted by maria's blue 直子 at 2019年05月10日 03:56
maria's blue 直子 さま
コメントありがとうございました。また、お気に入りに入れて頂き、お読み頂いているとのこと、恐縮です。こちらこそありがとうございます。
私も地元の伝承などが好きで、自分なりに文献を調べて書いておりますが、なんといっても素人なもので、誤謬や見当違いのことも多々あるかと思います。もしそういうことがありましたらご教示頂けると大変嬉しいです。
世界の巨人伝説もお詳しいのですね!
私も、maria's blue 直子さんと同じく、懐かしい気がします(^o^)。
たぶん、その土地を作った「大地の神」信仰(古代の信仰?)に繋がる精神性があって、懐かしく感じられるのかもしれませんね。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
コメントありがとうございました。また、お気に入りに入れて頂き、お読み頂いているとのこと、恐縮です。こちらこそありがとうございます。
私も地元の伝承などが好きで、自分なりに文献を調べて書いておりますが、なんといっても素人なもので、誤謬や見当違いのことも多々あるかと思います。もしそういうことがありましたらご教示頂けると大変嬉しいです。
世界の巨人伝説もお詳しいのですね!
私も、maria's blue 直子さんと同じく、懐かしい気がします(^o^)。
たぶん、その土地を作った「大地の神」信仰(古代の信仰?)に繋がる精神性があって、懐かしく感じられるのかもしれませんね。
これからもどうぞよろしくお願いいたします。
Posted by かるだ もん at 2019年05月12日 19:28
at 2019年05月12日 19:28
 at 2019年05月12日 19:28
at 2019年05月12日 19:28※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム