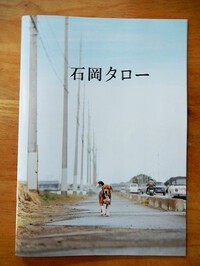2012年02月29日
つくば近郊 だいだらぼっちの足跡を探して(1)
(つくば・茨城 プチ民俗学) つくば近郊 だいだらぼっちの足跡を探して(1)
(初出:2012年2月29日 19時23分)
(2012年1月29日放送 ラヂオつくば「つくば井戸端レポーター」の放送内容を再構築しています。)
だいだらぼっちってご存知ですか?
だいだらぼう、でーだらぼう・・・とも呼ばれ、山や池を作った伝説の巨人として、日本国内各地に伝わっています(文献1)。
呼び方もいろいろバリエーションがあるようですが、ここでは「だいだらぼっち」とします。
スタジオジブリの「もののけ姫」にも出てきますね。
だいだらぼっちの伝説は、奈良時代に書かれた常陸国風土記にも大串の貝塚のいわれをはじめ、茨城県内でもいくつも「だいだらぼっち」にまつわる土地があります。
水戸付近、県北に伝わる話がよく知られているようですね。
というわけで、今回は、知られざるつくばでの伝説、そしてその周辺の県南県西に伝わる「だいだらぼっち」伝説の地を訪ねてみました。
今回初公開となるかもしれない場所もあります!?
(はじめに)
関東平野で富士山と筑波山が両方ともよく見えるエリアでの 2つのストーリーのパターン
茨城県南、県西地区では、筑波山はもちろん、冬の晴れた日は富士山もはっきり見えます。
だいだらぼっちの話は、どうもいくつかのパターンに分類できるように思いますが、特に、関東平野で富士山と筑波山が両方ともよく見えるエリアだと、次の2つのパターンに分かれるように思います。
① 筑波山に腰かけたので、山頂が2つに分かれた。また足跡が、池、くぼ地、湿地になった。
② 富士山と筑波山の重さを天秤棒を使って比べようとしたら、筑波山が天秤から落ちたため、山頂が2つに分かれた。また、測る時にふんばってついた足跡が、池、くぼ地、湿地になった。
③ その他のパターン
①は筑波山に非常に近い土地ならでは物語のように感じます。
②は、より広いエリアで伝わっている話のパターンのようです。土地によっては、筑波山の代わりに、その土地ならではの山だったり、または富士山単独だったりするようです。
③はまたいくつパターンがあり、興味深いものもありますが、これはまた機会がありましたら。
以上を頭に入れて、だいだらぼっちの足跡を訪ねてみました。(今回の写真は2012年1月初旬撮影)
1.つくばに伝わる、だいだらぼっちの伝説
(1)つくば市大曾根 おはぐろ池、おはぐろ坂付近(物語パターン①)
同じつくば市民レポーターの鬼丸のりぞうさんと、鬼丸さんのお母さんより、だいだらぼう伝説を、直接うかがい、場所に連れて頂ける機会がありました。
ストーリーは
「筑波山にこしかけた時に山の真ん中が凹んで男体山と女体山に別れた。そしてその時足を置いた跡が、大曾根の近くの窪地。もうひとつの足跡は真壁の方にあると言われている。」
(2011年8月に放送された、ラヂオつくば「ブラのり散歩」の大穂地区編で紹介されました)
「筑波歴史散歩」(文献2)では「おはぐろ池(今はない)」の由来として、同じストーリーの伝承が紹介されています。
どちらも先に書いた伝承パターン①です。
 「おはぐろ坂」
「おはぐろ坂」
旧大穂町大曽根から、旧筑波町小田方面に行く旧道とのことです。
台地にある大曽根から、桜川に降りていくため、坂道のなっていて、この坂を、地元では「おはぐろ坂」と呼んでいるそうです。
おはぐろ坂の脇に、「だいだらぼっちの足跡」と呼ばれるくぼ地が近年まであったと、地元の方のお話です。
 また文献2によると、おはぐろ坂の脇に「おはぐろ池」と呼ばれる池が昔あって、「だいらだぼっちの足跡」と言われていたとのことです。
また文献2によると、おはぐろ坂の脇に「おはぐろ池」と呼ばれる池が昔あって、「だいらだぼっちの足跡」と言われていたとのことです。
したがって近年まであったくぼ地が、「おはぐろ池」なのでしょう。
今は霊園となって、造成されてその痕跡はありません。
さて、霊園のそばには、塚らしい場所や、古墳の石棺らしい石がありました。
実際、このあたりは遺跡が発掘されています(文献3)。
 「おはぐろ池」があった付近から土浦方面を望む。
「おはぐろ池」があった付近から土浦方面を望む。
大変見晴らしのよい場所です。
このあたりは、小田山(宝鏡山)がすぐ近くに見え、その北に筑波山も見える場所です。
(2)おはぐろ池の対をなす、候補1.つくば市安食 あしこ池
文献2に「あしこ池」として紹介されています。大穂の「おはぐろ池」の対をなす、もうひとつの「だいだらぼっちの足跡」。
地図上には「あしこ池」という名の池はないようです。
そこで、文献4の「安食村」を見ると、「あしこ池」はないのですが、「足黒池」という名前の記載があります。「あしぐろ」→ 「あしこ」」となったように思うんですが、どうでしょうか。
その足黒池はどこかというと・・・
 地図から「足黒池」と同定される池。
地図から「足黒池」と同定される池。
現在は(独)産業技術総合研究所 北サイトの敷地内なので、残念ながら一般には見られません。
 木々に囲まれ、人里はなれた静かな場所で、野鳥の楽園となっておりました。
木々に囲まれ、人里はなれた静かな場所で、野鳥の楽園となっておりました。
ある意味、昔のままの姿が保たれているのかもしれません。
別の文献(文献5)によると、足黒池は、その他の池とともに、農業用水として江戸(?)時代整備されたものとも言います。
もともと沼地や湿地だった場所に水を溜めたとしたら、もとの沼地や湿地に、だいだらぼっちにまつわる伝説があったのかもしれません。
以上、安食の「あしこ池」が「足黒池」だとして、話を進めてみました。
また、「あしこ池」=「足黒池」だとすると、偶然かもしれませんがが、大穂の「おはぐろ池」、安食の「あしぐろ池」で、何となく対になっている名前であるのも興味深いです。
(3) 候補2.真壁の方にあるという、だいだらぼっちのもうひとつの足はどこか?
、
地元の方がおっしゃる「大穂・おはぐろ池」と対をなす、真壁にあるという足跡」はどこなのでしょうか?
文献を当たっていますが、現在のところ該当する場所や話は見当たりません。文献に載っていない地元に伝わる伝承があるのかもしれませんが。
そこで、試しに2つ候補を考えてみました。
【候補2-①】 (旧)真壁町(現 桜川市)の長者池付近?
だいだらぼっちは「筑波山に腰をかけた」のですから、左足が、(旧)大穂町大曾根付近とすると、右足がどこあたりに来るか・・・。
ということで、無理やり(^^;)、筑波山の男体山・女体山の間付近を頂点に、一つの点を大穂のおはぐろ池にして、二等辺三角形をおおざっぱに地図上で描いてみると、おはぐろ池と対称する位置付近に、良い感じに(?)、真壁の「長者池」、「国王池」があります(文献6)。
長者池は、付近の土地に長者伝説が伝わっています(文献7)。
国王池の云われは、まだ現在不明。
実際現地に行ってみました。
大きさは長者池の方が大きいですが、「窪地」としては国王池の方が足跡っぽい印象ではあります(あくまでの主観 ^^;)。
文献の載っていない、地元の伝承を知りたいところです。地元でご存知の方、教えて頂けると幸いです。
 長者池。
長者池。
遠くに筑波山が見えます。
桜の樹が植えられていて、桜の季節の頃は見ものでしょう。
釣りをする人が見受けられました。
揚水施設が近くにありました(霞ヶ浦用水による池のようです)
 国王池。
国王池。
畑の中の窪地。というか、地形的には桜川の浅い谷津のように見えます。
 国王池付近から筑波山を望む。
国王池付近から筑波山を望む。
【候補2-②】 (旧)真壁郡大和村(現 桜川市)大曽根?
真壁町ではありませんが、「真壁の方」ということなら、範囲を広げて真壁郡と考えると、「旧真壁郡大和村」にその名も「大曽根」という場所があります。
江戸時代まで「大曽根村」。雨引観音の近くです。このあたりも地図を見ると小さな池や湿地があります。
文献8によるとそれらの池は、江戸時代に作られた農業用ため池のようです。
ただ、もともと水を貯めやすい窪地、湿地、小さな池はあった可能性はあるでしょう。
また、例えば「大曽根」つながりで、だいだらぼうの足跡もセットで語られた可能性はどうでしょうか。
「大曽根つながりで、こういう話が語られ伝わった」と考えると、何だか楽しくなるのですが。
ここもまだ文献では伝承は分からないので、文献にない地元の伝承が知りたいところです。
さて、次回は、さらに、県南、県西地区の、だいだらぼっち伝説の地を訪ねます。お楽しみに。
→ つくば近郊 だいだらぼっちの足跡を探して(2)
今回訪ねた場所の地図は → http://g.co/maps/y7wke
-----------------------------------------------------------------------
参考文献
1.「だいだらぼうの足跡」 柳田國男 (現代日本文学大系20 柳田國男集」) 筑摩書房
2.「筑波歴史散歩」 宮本宣一著 宮本宣一遺稿刊行会 崙書房
3.「つくば市遺跡地図」 つくば市教育委員会
4.「筑波郡郷土史」塙泉嶺編 賢美閣
5.「角川日本地名大辞典8 茨城県」 角川書店
6.「スーパーマップル 1/1万 茨城県道路地図」 (2000年4月発行)
7.「真壁の昔ばなし」 仲田 安夫著 筑波書林
8.「大曽根雑記」岡村 安久 筑波書林
(初出:2012年2月29日 19時23分)
(2012年1月29日放送 ラヂオつくば「つくば井戸端レポーター」の放送内容を再構築しています。)
だいだらぼっちってご存知ですか?
だいだらぼう、でーだらぼう・・・とも呼ばれ、山や池を作った伝説の巨人として、日本国内各地に伝わっています(文献1)。
呼び方もいろいろバリエーションがあるようですが、ここでは「だいだらぼっち」とします。
スタジオジブリの「もののけ姫」にも出てきますね。
だいだらぼっちの伝説は、奈良時代に書かれた常陸国風土記にも大串の貝塚のいわれをはじめ、茨城県内でもいくつも「だいだらぼっち」にまつわる土地があります。
水戸付近、県北に伝わる話がよく知られているようですね。
というわけで、今回は、知られざるつくばでの伝説、そしてその周辺の県南県西に伝わる「だいだらぼっち」伝説の地を訪ねてみました。
今回初公開となるかもしれない場所もあります!?
(はじめに)
関東平野で富士山と筑波山が両方ともよく見えるエリアでの 2つのストーリーのパターン
茨城県南、県西地区では、筑波山はもちろん、冬の晴れた日は富士山もはっきり見えます。
だいだらぼっちの話は、どうもいくつかのパターンに分類できるように思いますが、特に、関東平野で富士山と筑波山が両方ともよく見えるエリアだと、次の2つのパターンに分かれるように思います。
① 筑波山に腰かけたので、山頂が2つに分かれた。また足跡が、池、くぼ地、湿地になった。
② 富士山と筑波山の重さを天秤棒を使って比べようとしたら、筑波山が天秤から落ちたため、山頂が2つに分かれた。また、測る時にふんばってついた足跡が、池、くぼ地、湿地になった。
③ その他のパターン
①は筑波山に非常に近い土地ならでは物語のように感じます。
②は、より広いエリアで伝わっている話のパターンのようです。土地によっては、筑波山の代わりに、その土地ならではの山だったり、または富士山単独だったりするようです。
③はまたいくつパターンがあり、興味深いものもありますが、これはまた機会がありましたら。
以上を頭に入れて、だいだらぼっちの足跡を訪ねてみました。(今回の写真は2012年1月初旬撮影)
1.つくばに伝わる、だいだらぼっちの伝説
(1)つくば市大曾根 おはぐろ池、おはぐろ坂付近(物語パターン①)
同じつくば市民レポーターの鬼丸のりぞうさんと、鬼丸さんのお母さんより、だいだらぼう伝説を、直接うかがい、場所に連れて頂ける機会がありました。
ストーリーは
「筑波山にこしかけた時に山の真ん中が凹んで男体山と女体山に別れた。そしてその時足を置いた跡が、大曾根の近くの窪地。もうひとつの足跡は真壁の方にあると言われている。」
(2011年8月に放送された、ラヂオつくば「ブラのり散歩」の大穂地区編で紹介されました)
「筑波歴史散歩」(文献2)では「おはぐろ池(今はない)」の由来として、同じストーリーの伝承が紹介されています。
どちらも先に書いた伝承パターン①です。
 「おはぐろ坂」
「おはぐろ坂」旧大穂町大曽根から、旧筑波町小田方面に行く旧道とのことです。
台地にある大曽根から、桜川に降りていくため、坂道のなっていて、この坂を、地元では「おはぐろ坂」と呼んでいるそうです。
おはぐろ坂の脇に、「だいだらぼっちの足跡」と呼ばれるくぼ地が近年まであったと、地元の方のお話です。
 また文献2によると、おはぐろ坂の脇に「おはぐろ池」と呼ばれる池が昔あって、「だいらだぼっちの足跡」と言われていたとのことです。
また文献2によると、おはぐろ坂の脇に「おはぐろ池」と呼ばれる池が昔あって、「だいらだぼっちの足跡」と言われていたとのことです。したがって近年まであったくぼ地が、「おはぐろ池」なのでしょう。
今は霊園となって、造成されてその痕跡はありません。
さて、霊園のそばには、塚らしい場所や、古墳の石棺らしい石がありました。
実際、このあたりは遺跡が発掘されています(文献3)。
 「おはぐろ池」があった付近から土浦方面を望む。
「おはぐろ池」があった付近から土浦方面を望む。大変見晴らしのよい場所です。
このあたりは、小田山(宝鏡山)がすぐ近くに見え、その北に筑波山も見える場所です。
(2)おはぐろ池の対をなす、候補1.つくば市安食 あしこ池
文献2に「あしこ池」として紹介されています。大穂の「おはぐろ池」の対をなす、もうひとつの「だいだらぼっちの足跡」。
地図上には「あしこ池」という名の池はないようです。
そこで、文献4の「安食村」を見ると、「あしこ池」はないのですが、「足黒池」という名前の記載があります。「あしぐろ」→ 「あしこ」」となったように思うんですが、どうでしょうか。
その足黒池はどこかというと・・・
 地図から「足黒池」と同定される池。
地図から「足黒池」と同定される池。現在は(独)産業技術総合研究所 北サイトの敷地内なので、残念ながら一般には見られません。
 木々に囲まれ、人里はなれた静かな場所で、野鳥の楽園となっておりました。
木々に囲まれ、人里はなれた静かな場所で、野鳥の楽園となっておりました。ある意味、昔のままの姿が保たれているのかもしれません。
別の文献(文献5)によると、足黒池は、その他の池とともに、農業用水として江戸(?)時代整備されたものとも言います。
もともと沼地や湿地だった場所に水を溜めたとしたら、もとの沼地や湿地に、だいだらぼっちにまつわる伝説があったのかもしれません。
以上、安食の「あしこ池」が「足黒池」だとして、話を進めてみました。
また、「あしこ池」=「足黒池」だとすると、偶然かもしれませんがが、大穂の「おはぐろ池」、安食の「あしぐろ池」で、何となく対になっている名前であるのも興味深いです。
(3) 候補2.真壁の方にあるという、だいだらぼっちのもうひとつの足はどこか?
、
地元の方がおっしゃる「大穂・おはぐろ池」と対をなす、真壁にあるという足跡」はどこなのでしょうか?
文献を当たっていますが、現在のところ該当する場所や話は見当たりません。文献に載っていない地元に伝わる伝承があるのかもしれませんが。
そこで、試しに2つ候補を考えてみました。
【候補2-①】 (旧)真壁町(現 桜川市)の長者池付近?
だいだらぼっちは「筑波山に腰をかけた」のですから、左足が、(旧)大穂町大曾根付近とすると、右足がどこあたりに来るか・・・。
ということで、無理やり(^^;)、筑波山の男体山・女体山の間付近を頂点に、一つの点を大穂のおはぐろ池にして、二等辺三角形をおおざっぱに地図上で描いてみると、おはぐろ池と対称する位置付近に、良い感じに(?)、真壁の「長者池」、「国王池」があります(文献6)。
長者池は、付近の土地に長者伝説が伝わっています(文献7)。
国王池の云われは、まだ現在不明。
実際現地に行ってみました。
大きさは長者池の方が大きいですが、「窪地」としては国王池の方が足跡っぽい印象ではあります(あくまでの主観 ^^;)。
文献の載っていない、地元の伝承を知りたいところです。地元でご存知の方、教えて頂けると幸いです。
 長者池。
長者池。遠くに筑波山が見えます。
桜の樹が植えられていて、桜の季節の頃は見ものでしょう。
釣りをする人が見受けられました。
揚水施設が近くにありました(霞ヶ浦用水による池のようです)
 国王池。
国王池。畑の中の窪地。というか、地形的には桜川の浅い谷津のように見えます。
 国王池付近から筑波山を望む。
国王池付近から筑波山を望む。【候補2-②】 (旧)真壁郡大和村(現 桜川市)大曽根?
真壁町ではありませんが、「真壁の方」ということなら、範囲を広げて真壁郡と考えると、「旧真壁郡大和村」にその名も「大曽根」という場所があります。
江戸時代まで「大曽根村」。雨引観音の近くです。このあたりも地図を見ると小さな池や湿地があります。
文献8によるとそれらの池は、江戸時代に作られた農業用ため池のようです。
ただ、もともと水を貯めやすい窪地、湿地、小さな池はあった可能性はあるでしょう。
また、例えば「大曽根」つながりで、だいだらぼうの足跡もセットで語られた可能性はどうでしょうか。
「大曽根つながりで、こういう話が語られ伝わった」と考えると、何だか楽しくなるのですが。
ここもまだ文献では伝承は分からないので、文献にない地元の伝承が知りたいところです。
さて、次回は、さらに、県南、県西地区の、だいだらぼっち伝説の地を訪ねます。お楽しみに。
→ つくば近郊 だいだらぼっちの足跡を探して(2)
今回訪ねた場所の地図は → http://g.co/maps/y7wke
-----------------------------------------------------------------------
参考文献
1.「だいだらぼうの足跡」 柳田國男 (現代日本文学大系20 柳田國男集」) 筑摩書房
2.「筑波歴史散歩」 宮本宣一著 宮本宣一遺稿刊行会 崙書房
3.「つくば市遺跡地図」 つくば市教育委員会
4.「筑波郡郷土史」塙泉嶺編 賢美閣
5.「角川日本地名大辞典8 茨城県」 角川書店
6.「スーパーマップル 1/1万 茨城県道路地図」 (2000年4月発行)
7.「真壁の昔ばなし」 仲田 安夫著 筑波書林
8.「大曽根雑記」岡村 安久 筑波書林
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム