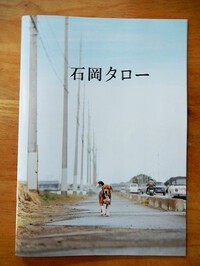2020年05月01日
筑波山麓を舞台にした古代の民衆ドラマ!蚕影山の「和気広虫」伝説
筑波山麓を舞台にした古代の民衆ドラマ!蚕影山の「和気広虫」伝説
****************************
昔話・伝説関係の話題を書く時に、私のモットーとして、
★なるべく文献にあたる。
★可能な限り、現地に行く。
を心がけていますが、この新型コロナウィルス禍で、図書館は閉館して書籍に当たれず、
外出もままならない状況です 。
。
でもせっかく家にいる時間も多いことですし、手持ちの書籍と、信用できそうなインターネットのサイトを使って、調べていこうと思います。
新型コロナウィルス禍が収まり、図書館の本も読めたり、現地に行ったりして、
新しいことが分かりましたら、随時、修正・更新するということにします 。
。
****************************
さて、前回までは、蚕影山神社にまつわる信仰の話を書きました。
 蚕影山神社と桑林寺 ~金色姫伝説の不思議
蚕影山神社と桑林寺 ~金色姫伝説の不思議
 つくば市フットパス『筑波山麓』で訪ねる 金色姫伝説の地
つくば市フットパス『筑波山麓』で訪ねる 金色姫伝説の地
有名な『金色姫伝説』に触れましたが、蚕影山神社及び神郡に関わる伝説として、
もう一つ『和気広虫伝説』があります(文献1)。
和気広虫は奈良時代の人。
奈良時代の有名な怪僧 弓削道鏡の天敵? 和気清麻呂のお姉さんで女官として孝謙上皇に仕えていました。
(Wikipediaより)
大変慈悲深い人 で、多くの孤児を養育したと伝えられています。
で、多くの孤児を養育したと伝えられています。
神郡に伝わる伝説は、和気広虫に直接関わる伝説ではなく、和気広虫に育てられた孤児が大人になって、この神郡に住んだことが発端の伝説ですが、とても興味深いのです。
神郡地区に伝わる和気広虫伝説
【あらすじ】 参考:文献1 『筑波歴史散歩』(宮本宣一 著)
和気広虫に育てられた孤児の一人が、瓦職人になって常陸国へ来て、
新治郡カワラエ村で石岡国分寺の瓦や北条中台の国分寺級の瓦を焼いていた。
筑波のふもとの娘を妻にし、神郡に移り住んで、瓦を焼く技術を土地の人に伝えた。
そして、自分を育ててくれた広虫を偲んで、近くの山に広虫の姿を祀り、拝んでいた。
広虫に育てられた『子』が広虫の姿『御影』を拝むので、その山は『コカゲ山』と呼ばれるようになった。
また、広虫(ヒロムシ)の『虫』から、子供の虫封じや、蚕の虫除けに効くとされてきた。
※『蚕を守る』のでなく、『蚕の虫除け』は何を指すのか不明ですが・・・。
● 新治郡カワラエ村はどこ?
伝わる伝説の時代は奈良後期から平安時代初頭。
当時の『新治郡』は古代『新治郡』(今の筑西市あたり)です。
しかし時代を経て人々が近代・現代まで口頭で伝えた話であること、
『常陸国分寺の瓦を焼いた』と具体的に伝わっていることもあり、常陸国府(今の石岡市)に近いと考えられるので、
この物語の『新治郡』は、やはり近代の『新治郡』を指すと考えて良いでしょう。
事実、旧新治郡八郷町(現 石岡市)には、『瓦会(かわらえ)村』がかつて実在しました。
参考: 石岡市HP『市の概要』
地図で確認すると、字名に『瓦会』はないようですが、石岡市瓦谷に、
瓦会小学校、瓦会郵便局、瓦会地区多目的研修センターがあり、『瓦会』の地名がついています。
更に そのすぐ近くに瓦塚窯跡があり、石岡の国分寺の瓦はここで焼かれていたとのこと!
そのすぐ近くに瓦塚窯跡があり、石岡の国分寺の瓦はここで焼かれていたとのこと!
参考: 石岡市HP 『瓦塚窯跡』
https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004833.html
茨城県教育委員会HP『瓦塚窯跡』
上記の石岡市HPによると、
『瓦塚窯跡は、主に奈良時代の天平13年(741)、常陸国府(現在の石岡市国府周辺)に
国分寺・国分尼寺等が建立された際に、その屋根に葺く瓦類を製造した窯跡です。
昭和12年(1937)に茨城県の史跡に指定されました』
そして、上記の茨城県教育委員会HPによると、
『瓦塚窯跡は、古代常陸国の窯跡である。昭和43年以降の 調査により、
南北130m、東西80mの範囲に合計35基の窯が築かれたことが判明した。
操業は7世紀前葉から10世紀前葉に及ぶ。 窯構造は大半が地下式窖窯(あながま)である』
とのこと。
瓦塚窯跡の住所は石岡市部原604番地1で、地図で確認する瓦谷に隣接する場所で、近くに瓦会小学校、瓦会郵便局があります。
地名も遺跡も一致するので、伝説の『カワラエ村』は旧瓦会村(現在の石岡市瓦谷地区とその周辺)として良いのではないでしょうか。
すごい!

瓦塚窯跡から南西方向へ2kmほど離れた場所にある、『佐久の大杉』(2015年5月撮影)
茨城県の指定天然記念物で、樹齢は推定1300年以上!
コロナ禍が収まったら、瓦塚窯跡を訪ねたいです。
その時はこのブログでまた紹介します

こちらは、瓦塚窯跡から南西方向へ3kmほど離れた場所にある丸山古墳にほど近い恋瀬川付近(2015年5月撮影)
ちなみに、この『丸山古墳』については、以前書いた記事も良かったら。
→ 茨城県最古級!‐丸山古墳(石岡・八郷) に行ってきました。
●神郡地区は、近年まで瓦の製造が盛んだった

神郡の町並み(2018年4月撮影)
文献2(すそみろく 第9号)の『瓦の灯りプロムナード 田井の瓦屋さんと子どもたち』という記事に興味深い話が載っています。
それによると、
・神郡がある田井地区、昔から瓦作りが盛んな土地だったとのこと。
・すぐそばを流れる逆川沿いに堆積した土は、瓦作りに適していたとのこと。

瓦作りに適した粘土が取れたという逆川
すごい
ここまでみごとに、伝説と実際の場所が一致しているのも珍しいですよね !?
!?
当時、本当に瓦職人の人が奈良から、はるばる常陸国の瓦会村に行き、実際、常陸国国府(今の石岡市)の国分寺・国分尼寺の
瓦を焼いたのかもしれませんね。


蚕影山周辺を望む(2018年4月撮影)
瓦職人になった彼は、自分を育ててくれた広虫の姿を山の中に祀って朝夕にお参りしたことから、
子が(育ててくれた人の)御影を拝む山→ こかげ山 と呼ばれようになる。
その『広虫』の『虫』から、やがて、子供の疳の虫(広虫が孤児を育てたということで、子供の神様になったか?)
や、絹を取るための蚕の守り神として信仰されるようになった → 『蚕影(こかげ)山』
という話。
私はかなり納得出来る話に思います!

蚕影山神社鳥居から、拝殿方向を撮る(2019年3月撮影)
金色姫伝説は、どうも江戸時代に入って広く流布したらしい(以前書いた記事参照)、比較的新しい伝説のようです。
金色姫伝説が流布するずっと前から、蚕影山には、素朴な『広虫』信仰があったと考える方が、納得出来ませんか?
古代の民衆史を読むようです !
!
ドラマに出来そうではありませんか
 。
。
● 奈良時代、カワラエ村で瓦を焼いていた職人は、どうやって神郡の娘と夫婦になったのか?
そして個人的に知りたいのは、どうやって神郡の女性と知り合ったか?ということ。
ここからは私の妄想ですが、やはり万葉集にもたくさん歌われる有名な古代の筑波山の『かがい(嬥歌)』が、
出会いの場だったりしたのではないでしょうか♪
今で言う合コンですから(^^)
しかも、万葉集に歌われる『あじくま山』は蚕影山に比定されるとのこと(以前書いた記事つくば市内 万葉集に詠われるもう一つの山 『あじくま山』 参照)。
いろんなことが見事に結びついて、なんだかワクワクしますね♪
うーん、やっぱり、筑波山地域を舞台にした、古代の民衆のドラマになりますよ

『かがい(嬥歌)』が行われた場所の有力な候補地 夫女が原にある『夫女石』
(2017年撮影)
神郡からほど近い場所にあります。
夫女が原は、現在は、つくば市の研修・宿泊施設 『筑波ふれあいの里』の敷地になっています。
なお、『かがい(嬥歌)』に関連した話題については、以前書いた記事も良かったら♪
→ つくば市内 万葉集に詠われるもう一つの山 『あじくま山』
つくば市内 万葉集に詠われるもう一つの山 『あじくま山』
 シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石
シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石
●和気広虫は、徳一上人とも繋がる!?
奈良時代後期、筑波山に寺を開創した徳一上人は、藤原仲麻呂(恵美押勝)の子と伝わります。
藤原仲麻呂(恵美押勝)は、藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)を起こして、一族もろとも死罪になりますが、
子供達のうち、まだ乳飲み子のだった下の二人は死罪を免れ、
その助命に奔走したのが和気広虫で、乳飲み子の一人が後の徳一上人になったそう(文献3)
徳一上人が藤原仲麻呂の子だというのは、『後世の付会』で『出自は不明というしかない』(文献4)とも言います。
ただ、もし一般に言われているように、徳一上人が藤原仲麻呂の子だとすると、ちょっと面白い人物相関図が見えてきます。

和気広虫の弟の和気清麻呂は、有名な宇佐八幡宮神託事件で弓削道鏡と対立し、孝謙天皇から名前を汚い名前に変えられた上に、
流刑になりますが、女官だった和気広虫も一緒に、やはり名前を変えられて流刑になります(二人とも天皇が代わった時に復帰)。
※この「名前を変える」という行為も、古代の言霊信仰にも関わるのか、とても興味深いのですが、ここでは触れません。
一方、徳一上人の父と言われる藤原仲麻呂も、恵美押勝と良い名前を貰えるくらい孝謙天皇に重用されますが、
結局、弓削道鏡が現れて、孝謙・道鏡と対立、これまた有名な藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)を起こして負けて死罪。
子供達も全員死罪になるところを、「必ず僧侶にする」を条件に、まだ幼かった下の二人の助命に奔走したのが和気広虫(文献2)。
たくさんの孤児を養育したり、謀反人の幼い子供の助命嘆願をしたり、
和気広虫は、なんと慈愛深く、しかも行動力のある女性だったのでしょう
私は一気に和気広虫のファンになりました
そして蚕影山神社の始まりは、
『和気広虫に育てられて、立派な瓦職人になった子どもが、広虫の像(御影)を山中に祀り、日々これにお参りした』
という謂われに、個人的に一票入れます
更に、徳一上人の生い立ちも和気広虫に関わるというならば、これは絶対に、筑波山麓舞台の古代民衆ドラマ作れちゃう♪
しかもかなり壮大な 。どなたか漫画で描いて下さい
。どなたか漫画で描いて下さい
● おまけ:茨城県下に伝わる孝謙天皇・弓削道鏡伝説
和気広虫の人生に大きく関わった、孝謙天皇(称徳天皇)と弓削道鏡。
道鏡は失脚した後、下野国(今の栃木県)に流され、下野薬師寺の別当になりそこで亡くなります(文献5)。
そのせいか、茨城の特に県央の辺りは、弓削道鏡や道鏡を寵愛した考謙天皇の伝説が伝わっています(文献5、6、7)。
古代の有名なスキャンダルの二人なので、伝説の内容も、あることないこと含む大人な話題なのですが、なかなか興味深いので、機会があったら考察してみたいです。
--------------------------
【参考文献】
1.『筑波歴史散歩』宮本宣一 著 日経事業出版センター
2.『すそみろく 第9号』 すそみろく編集委員会
3.『続 新治村の昔ばなし』 伊藤三雄 著 田宮郷土史研究会
4.『筑波町史 上』
5.『常陽藝文 2020年4月号』 常陽藝文センター
6.『茨城の史跡と伝説』 茨城新聞社編 暁印書館
7.『常陸の伝説』 藤田稔 編著 第一法規
****************************
昔話・伝説関係の話題を書く時に、私のモットーとして、
★なるべく文献にあたる。
★可能な限り、現地に行く。
を心がけていますが、この新型コロナウィルス禍で、図書館は閉館して書籍に当たれず、
外出もままならない状況です
 。
。でもせっかく家にいる時間も多いことですし、手持ちの書籍と、信用できそうなインターネットのサイトを使って、調べていこうと思います。
新型コロナウィルス禍が収まり、図書館の本も読めたり、現地に行ったりして、
新しいことが分かりましたら、随時、修正・更新するということにします
 。
。****************************
さて、前回までは、蚕影山神社にまつわる信仰の話を書きました。
 蚕影山神社と桑林寺 ~金色姫伝説の不思議
蚕影山神社と桑林寺 ~金色姫伝説の不思議 つくば市フットパス『筑波山麓』で訪ねる 金色姫伝説の地
つくば市フットパス『筑波山麓』で訪ねる 金色姫伝説の地 有名な『金色姫伝説』に触れましたが、蚕影山神社及び神郡に関わる伝説として、
もう一つ『和気広虫伝説』があります(文献1)。
和気広虫は奈良時代の人。
奈良時代の有名な怪僧 弓削道鏡の天敵? 和気清麻呂のお姉さんで女官として孝謙上皇に仕えていました。
(Wikipediaより)
大変慈悲深い人
 で、多くの孤児を養育したと伝えられています。
で、多くの孤児を養育したと伝えられています。神郡に伝わる伝説は、和気広虫に直接関わる伝説ではなく、和気広虫に育てられた孤児が大人になって、この神郡に住んだことが発端の伝説ですが、とても興味深いのです。

神郡地区に伝わる和気広虫伝説
【あらすじ】 参考:文献1 『筑波歴史散歩』(宮本宣一 著)
和気広虫に育てられた孤児の一人が、瓦職人になって常陸国へ来て、
新治郡カワラエ村で石岡国分寺の瓦や北条中台の国分寺級の瓦を焼いていた。
筑波のふもとの娘を妻にし、神郡に移り住んで、瓦を焼く技術を土地の人に伝えた。
そして、自分を育ててくれた広虫を偲んで、近くの山に広虫の姿を祀り、拝んでいた。
広虫に育てられた『子』が広虫の姿『御影』を拝むので、その山は『コカゲ山』と呼ばれるようになった。
また、広虫(ヒロムシ)の『虫』から、子供の虫封じや、蚕の虫除けに効くとされてきた。
※『蚕を守る』のでなく、『蚕の虫除け』は何を指すのか不明ですが・・・。
● 新治郡カワラエ村はどこ?
伝わる伝説の時代は奈良後期から平安時代初頭。
当時の『新治郡』は古代『新治郡』(今の筑西市あたり)です。
しかし時代を経て人々が近代・現代まで口頭で伝えた話であること、
『常陸国分寺の瓦を焼いた』と具体的に伝わっていることもあり、常陸国府(今の石岡市)に近いと考えられるので、
この物語の『新治郡』は、やはり近代の『新治郡』を指すと考えて良いでしょう。
事実、旧新治郡八郷町(現 石岡市)には、『瓦会(かわらえ)村』がかつて実在しました。
参考: 石岡市HP『市の概要』
地図で確認すると、字名に『瓦会』はないようですが、石岡市瓦谷に、
瓦会小学校、瓦会郵便局、瓦会地区多目的研修センターがあり、『瓦会』の地名がついています。
更に
 そのすぐ近くに瓦塚窯跡があり、石岡の国分寺の瓦はここで焼かれていたとのこと!
そのすぐ近くに瓦塚窯跡があり、石岡の国分寺の瓦はここで焼かれていたとのこと!参考: 石岡市HP 『瓦塚窯跡』
https://www.city.ishioka.lg.jp/page/page004833.html
茨城県教育委員会HP『瓦塚窯跡』
上記の石岡市HPによると、
『瓦塚窯跡は、主に奈良時代の天平13年(741)、常陸国府(現在の石岡市国府周辺)に
国分寺・国分尼寺等が建立された際に、その屋根に葺く瓦類を製造した窯跡です。
昭和12年(1937)に茨城県の史跡に指定されました』
そして、上記の茨城県教育委員会HPによると、
『瓦塚窯跡は、古代常陸国の窯跡である。昭和43年以降の 調査により、
南北130m、東西80mの範囲に合計35基の窯が築かれたことが判明した。
操業は7世紀前葉から10世紀前葉に及ぶ。 窯構造は大半が地下式窖窯(あながま)である』
とのこと。
瓦塚窯跡の住所は石岡市部原604番地1で、地図で確認する瓦谷に隣接する場所で、近くに瓦会小学校、瓦会郵便局があります。
地名も遺跡も一致するので、伝説の『カワラエ村』は旧瓦会村(現在の石岡市瓦谷地区とその周辺)として良いのではないでしょうか。
すごい!


瓦塚窯跡から南西方向へ2kmほど離れた場所にある、『佐久の大杉』(2015年5月撮影)
茨城県の指定天然記念物で、樹齢は推定1300年以上!
コロナ禍が収まったら、瓦塚窯跡を訪ねたいです。
その時はこのブログでまた紹介します


こちらは、瓦塚窯跡から南西方向へ3kmほど離れた場所にある丸山古墳にほど近い恋瀬川付近(2015年5月撮影)
ちなみに、この『丸山古墳』については、以前書いた記事も良かったら。
→ 茨城県最古級!‐丸山古墳(石岡・八郷) に行ってきました。
●神郡地区は、近年まで瓦の製造が盛んだった
神郡の町並み(2018年4月撮影)
文献2(すそみろく 第9号)の『瓦の灯りプロムナード 田井の瓦屋さんと子どもたち』という記事に興味深い話が載っています。
それによると、
・神郡がある田井地区、昔から瓦作りが盛んな土地だったとのこと。
・すぐそばを流れる逆川沿いに堆積した土は、瓦作りに適していたとのこと。

瓦作りに適した粘土が取れたという逆川
すごい

ここまでみごとに、伝説と実際の場所が一致しているのも珍しいですよね
 !?
!?当時、本当に瓦職人の人が奈良から、はるばる常陸国の瓦会村に行き、実際、常陸国国府(今の石岡市)の国分寺・国分尼寺の
瓦を焼いたのかもしれませんね。


蚕影山周辺を望む(2018年4月撮影)
瓦職人になった彼は、自分を育ててくれた広虫の姿を山の中に祀って朝夕にお参りしたことから、
子が(育ててくれた人の)御影を拝む山→ こかげ山 と呼ばれようになる。
その『広虫』の『虫』から、やがて、子供の疳の虫(広虫が孤児を育てたということで、子供の神様になったか?)
や、絹を取るための蚕の守り神として信仰されるようになった → 『蚕影(こかげ)山』
という話。
私はかなり納得出来る話に思います!


蚕影山神社鳥居から、拝殿方向を撮る(2019年3月撮影)
金色姫伝説は、どうも江戸時代に入って広く流布したらしい(以前書いた記事参照)、比較的新しい伝説のようです。
金色姫伝説が流布するずっと前から、蚕影山には、素朴な『広虫』信仰があったと考える方が、納得出来ませんか?
古代の民衆史を読むようです
 !
!ドラマに出来そうではありませんか

 。
。● 奈良時代、カワラエ村で瓦を焼いていた職人は、どうやって神郡の娘と夫婦になったのか?
そして個人的に知りたいのは、どうやって神郡の女性と知り合ったか?ということ。
ここからは私の妄想ですが、やはり万葉集にもたくさん歌われる有名な古代の筑波山の『かがい(嬥歌)』が、
出会いの場だったりしたのではないでしょうか♪

今で言う合コンですから(^^)
しかも、万葉集に歌われる『あじくま山』は蚕影山に比定されるとのこと(以前書いた記事つくば市内 万葉集に詠われるもう一つの山 『あじくま山』 参照)。
いろんなことが見事に結びついて、なんだかワクワクしますね♪
うーん、やっぱり、筑波山地域を舞台にした、古代の民衆のドラマになりますよ


『かがい(嬥歌)』が行われた場所の有力な候補地 夫女が原にある『夫女石』
(2017年撮影)
神郡からほど近い場所にあります。
夫女が原は、現在は、つくば市の研修・宿泊施設 『筑波ふれあいの里』の敷地になっています。
なお、『かがい(嬥歌)』に関連した話題については、以前書いた記事も良かったら♪
→
 つくば市内 万葉集に詠われるもう一つの山 『あじくま山』
つくば市内 万葉集に詠われるもう一つの山 『あじくま山』 シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石
シリーズ「筑波山名跡誌に書かれた場所を訪ねて」 (3)夫女之原、夫女石●和気広虫は、徳一上人とも繋がる!?
奈良時代後期、筑波山に寺を開創した徳一上人は、藤原仲麻呂(恵美押勝)の子と伝わります。
藤原仲麻呂(恵美押勝)は、藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)を起こして、一族もろとも死罪になりますが、
子供達のうち、まだ乳飲み子のだった下の二人は死罪を免れ、
その助命に奔走したのが和気広虫で、乳飲み子の一人が後の徳一上人になったそう(文献3)
徳一上人が藤原仲麻呂の子だというのは、『後世の付会』で『出自は不明というしかない』(文献4)とも言います。
ただ、もし一般に言われているように、徳一上人が藤原仲麻呂の子だとすると、ちょっと面白い人物相関図が見えてきます。

和気広虫の弟の和気清麻呂は、有名な宇佐八幡宮神託事件で弓削道鏡と対立し、孝謙天皇から名前を汚い名前に変えられた上に、
流刑になりますが、女官だった和気広虫も一緒に、やはり名前を変えられて流刑になります(二人とも天皇が代わった時に復帰)。
※この「名前を変える」という行為も、古代の言霊信仰にも関わるのか、とても興味深いのですが、ここでは触れません。
一方、徳一上人の父と言われる藤原仲麻呂も、恵美押勝と良い名前を貰えるくらい孝謙天皇に重用されますが、
結局、弓削道鏡が現れて、孝謙・道鏡と対立、これまた有名な藤原仲麻呂の乱(恵美押勝の乱)を起こして負けて死罪。
子供達も全員死罪になるところを、「必ず僧侶にする」を条件に、まだ幼かった下の二人の助命に奔走したのが和気広虫(文献2)。
たくさんの孤児を養育したり、謀反人の幼い子供の助命嘆願をしたり、
和気広虫は、なんと慈愛深く、しかも行動力のある女性だったのでしょう

私は一気に和気広虫のファンになりました

そして蚕影山神社の始まりは、
『和気広虫に育てられて、立派な瓦職人になった子どもが、広虫の像(御影)を山中に祀り、日々これにお参りした』
という謂われに、個人的に一票入れます

更に、徳一上人の生い立ちも和気広虫に関わるというならば、これは絶対に、筑波山麓舞台の古代民衆ドラマ作れちゃう♪
しかもかなり壮大な
 。どなたか漫画で描いて下さい
。どなたか漫画で描いて下さい
● おまけ:茨城県下に伝わる孝謙天皇・弓削道鏡伝説
和気広虫の人生に大きく関わった、孝謙天皇(称徳天皇)と弓削道鏡。
道鏡は失脚した後、下野国(今の栃木県)に流され、下野薬師寺の別当になりそこで亡くなります(文献5)。
そのせいか、茨城の特に県央の辺りは、弓削道鏡や道鏡を寵愛した考謙天皇の伝説が伝わっています(文献5、6、7)。
古代の有名なスキャンダルの二人なので、伝説の内容も、あることないこと含む大人な話題なのですが、なかなか興味深いので、機会があったら考察してみたいです。
--------------------------
【参考文献】
1.『筑波歴史散歩』宮本宣一 著 日経事業出版センター
2.『すそみろく 第9号』 すそみろく編集委員会
3.『続 新治村の昔ばなし』 伊藤三雄 著 田宮郷土史研究会
4.『筑波町史 上』
5.『常陽藝文 2020年4月号』 常陽藝文センター
6.『茨城の史跡と伝説』 茨城新聞社編 暁印書館
7.『常陸の伝説』 藤田稔 編著 第一法規
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (三)
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (二)
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (一)
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(9) 地元の方から教えて頂いた神栖に伝わるお話
国立歴史民俗博物館 企画展 『陰陽師とは何者か』 を見て
映画『石岡タロー』
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (二)
落語『紋三郎稲荷』 の舞台を訪ねて (一)
茨城3つの養蚕信仰の聖地について(9) 地元の方から教えて頂いた神栖に伝わるお話
国立歴史民俗博物館 企画展 『陰陽師とは何者か』 を見て
映画『石岡タロー』
Posted by かるだ もん at 21:49│Comments(0)│茨城&つくば プチ民俗学・歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム